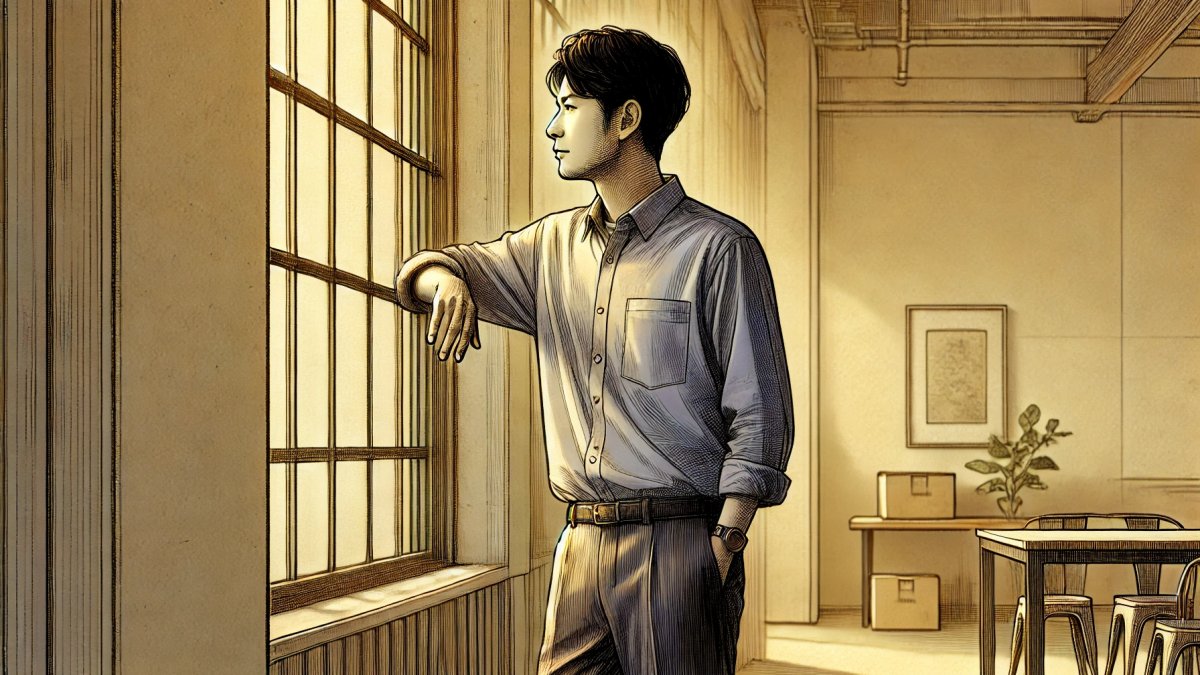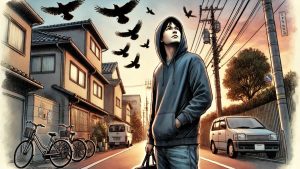「自分がこれだけできるのだから、他の人も同じようにできるはずだ」
「どうして、こんな簡単なことができないのだろう?」
あなたは、無意識のうちにこのように考えて、他人に対して苛立ちを感じたり、人間関係に悩んだりした経験はありませんか。
この「自分ができることは他人もできる」という考え方は、時に上司から部下への期待として現れ、意図せずパワハラと受け取られるケースもあります。
一方で、自分自身に対して「誰でもできることしかできない」「自分にできることは何もない」と過度に低い自己評価を下し、自信を失ってしまう人も少なくありません。
こうした自己評価の低さは、自分を大切にしていない人の特徴とも重なります。
実は、「自分がそうだから他人も」という思考パターンや、他者に自分と同じレベルを求める心理の背景には、心理学的な要因が隠されています。
また、これとは逆に「自分ができないことを他人に求める」ことわざが示すような、矛盾した状況に陥ることもあります。
この記事では、なぜこのような思い込みが生じるのか、その原因を深く掘り下げます。
そして、健全な自信がある人の性格の特徴を参考にしながら、自分と他人の能力を客観的に捉え、より良い人間関係を築くための具体的なヒントを探っていきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。
- 「自分ができることは他人もできる」と思う心理的背景
- その思い込みが人間関係に及ぼす具体的な悪影響
- 自己肯定感を高め、他者との健全な距離を保つ方法
- 自分と他人の能力を客観的に見るための具体的な視点
「自分ができることは他人もできる」と思う心理と原因
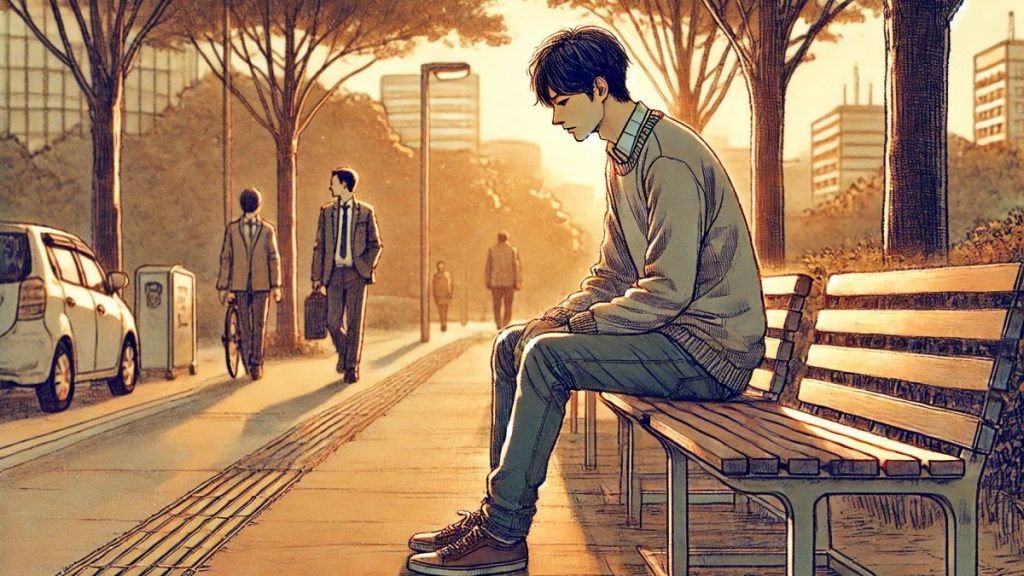
ここでは、なぜ「自分ができることは他人もできる」という特有の思考に陥ってしまうのか、その心理的な背景と具体的な原因について、多角的に掘り下げていきます。
- 自分がそうだから他人も、という心理学
- 「これくらい誰でもできる」という思い込み
- 自分を大切にしていない人の特徴
- 「誰でもできることしかできない」という無力感
- 「自分にできることは何もない」と感じる心理
自分がそうだから他人も、という心理学
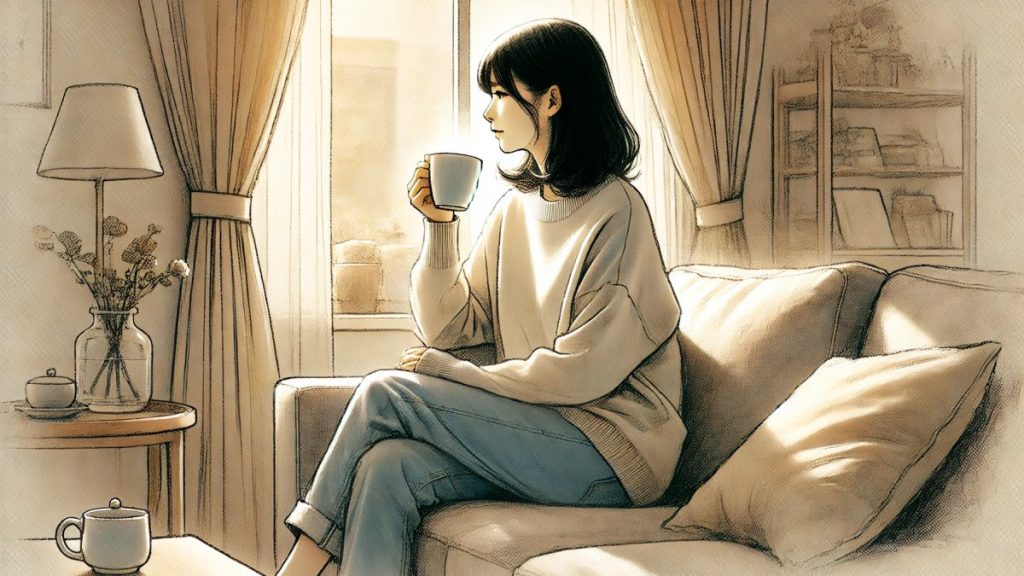
人はなぜ、「自分が基準」で物事を考えてしまうのでしょうか。
これには、私たちの脳が持つ思考のクセ、すなわち「認知バイアス」が深く関わっています。
認知バイアスとは、物事を判断する際に、無意識のうちに非合理的な思い込みや先入観に影響されてしまう心理現象のことです。
例えば、自分の意見や考えが、世間一般の常識であるかのように錯覚してしまう「偽の合意効果(False Consensus Effect)」というものがあります。
自分が難なくできることは、周りの人も同じようにできるはずだと考えてしまうのは、このバイアスが働いている一例と考えられます。
自分の経験や能力が、判断の際の最もアクセスしやすい情報であるため、脳が効率化のために「自分=多数派」という近道を選んでしまうのです。
また、ある特定分野で優秀な人を見ると、他の全ての面でも優れているに違いないと思い込んでしまう「ハロー効果」も関係します。
逆に、自分がある分野で何かを達成できた場合、「こんな自分にできたのだから、もっと優秀に見えるあの人なら当然できるだろう」と、他者の能力を過大評価してしまうことにも繋がります。
このように、「自分がそうだから他人も」という考えは、怠慢や傲慢さから来るのではなく、人間の脳が持つ自然な働きの一部なのです。
ただし、この心理的なクセを自覚しないままでいると、他者への誤解や過度な期待を生む原因となります。
もっと体系的に認知バイアスを学びたい人は、古典的名著『ファスト&スロー(上)』が基礎を押さえるのに役立ちます。
「これくらい誰でもできる」という思い込み
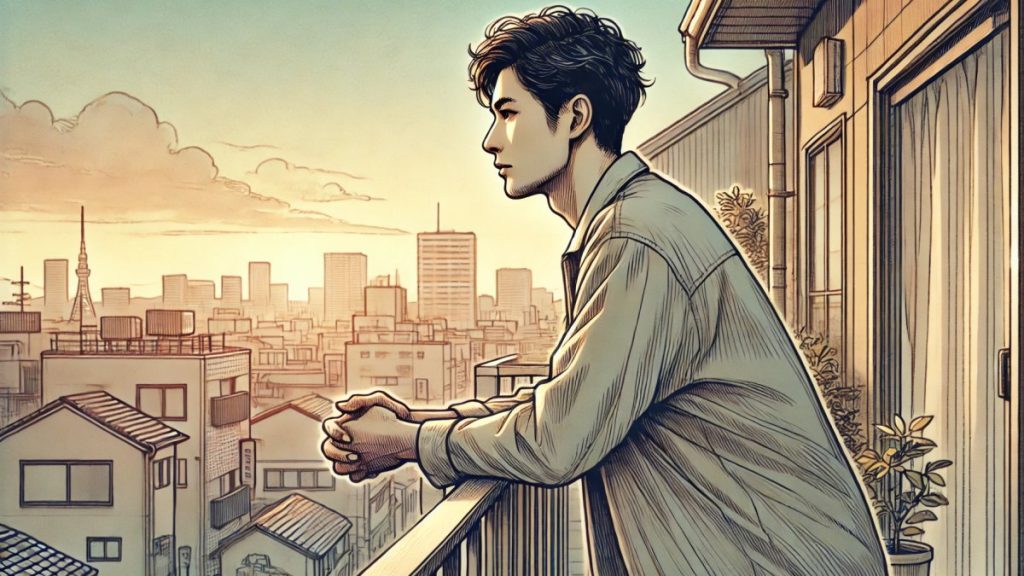
「冷蔵庫の残り物で料理を作る」「パソコンの簡単なトラブルを解決する」「時間通りに待ち合わせ場所に行く」。
これらが当たり前にできる人にとって、できない人がいることは想像しにくいかもしれません。
「これくらい誰でもできる」という感覚は、多くの場合、自己肯定感の低さからくる自己の能力の過小評価が原因です。
自分に自信がない人は、自分が持つスキルや能力を「大したことではない」と捉えがちです。
そのため、「こんな平凡な自分にできることは、当然、他の誰にでもできるはずだ」という論理に陥りやすくなります。
自分の成し遂げた努力や、習得したスキルを正当に評価できていないのです。
国内の最新調査でも、若者層で「自分に満足している」割合が国際比較で低い傾向が示されており、自己評価の下がりやすさが背景にあると読み取れます。
この思い込みは、本人にとっては謙遜のつもりかもしれませんが、他者に対しては非常に厳しい要求となる危険性をはらんでいます。
例えば、後輩に仕事を教える際に「こんな簡単なことも分からないの?」と感じてしまうのは、自分の習熟度を基準にしているためです。
実際には、その後輩がそのスキルを習得するには、自分と同じか、それ以上の時間と努力が必要なのかもしれません。
自分の「当たり前」は、決して他人の「当たり前」ではないという事実を認識することが、この思い込みから抜け出す第一歩となります。
自分が持つスキルは、大小にかかわらず、価値のあるものだと認める視点が大切です。
自分を大切にしていない人の特徴
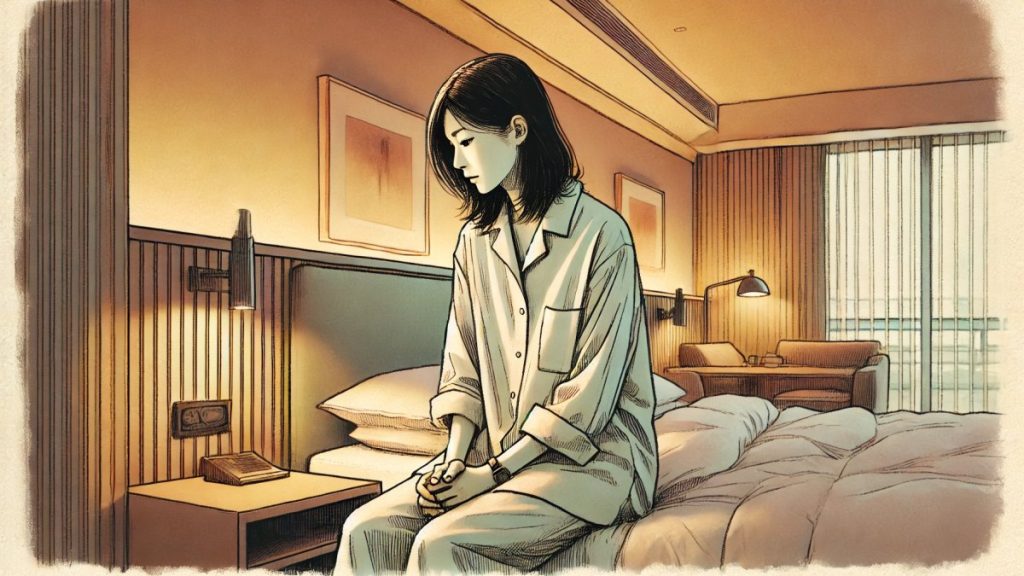
「自分ができることは他人もできる」という考え方の根底には、しばしば自己肯定感の低さ、つまり自分を大切にしていないという心理状態が横たわっています。
自分を大切にできない人は、自分の価値を低く見積もるため、自分の行動や能力も過小評価してしまう傾向があります。
自分を大切にしていない人の特徴として、まず挙げられるのが、他者からの評価を過度に気にすることです。
自分の価値を自分自身で認められないため、他人の承認によって自分の存在価値を確認しようとします。
その結果、自分の意見を主張できず、常に他人軸で行動してしまいます。
また、完璧主義に陥りやすいのも特徴の一つです。
自分に価値がないと感じているため、「何かを完璧に成し遂げなければ、自分は認められない」という強迫観念に駆られます。
この完璧主義が、自分だけでなく他人にも向けられると、「自分はこれだけやっているのだから、あなたも完璧にできて当然だ」という厳しい要求に繋がります。
さらに、自分の感情や欲求を後回しにする傾向もあります。
「自分が我慢すれば丸く収まる」と考え、ストレスや不満を溜め込みがちです。
このように自分を抑圧することが常態化すると、他人が自分の感情を素直に表現しているのを見たときに、理解できずに苛立ちを感じる原因にもなり得ます。
これらの特徴は、自分自身を正当に評価し、尊重することの難しさを示しています。
自己肯定感を根拠のない自信ではなく、自分への思いやりの態度として育てたい人には、研究に基づく実践書『セルフ・コンパッション』がおすすめです。
「誰でもできることしかできない」という無力感

「自分には特別な才能は何もない。
誰でもできることしかできない」という感覚は、深い無力感と結びついています。
この感情は、特に自分より優秀だと感じる人々に囲まれた環境や、常に他者との比較を意識してしまう状況で強まる傾向があります。
この無力感の根源は、多くの場合、自分の価値を「独自性」や「希少性」のみで測ろうとすることにあります。
例えば、多くの人が英語を話せる現代において、「英語が話せる」というだけでは特別なスキルではないと感じるかもしれません。
しかし、事務処理を正確に行いながら、英語で電話対応もできるとなれば、それは複数のスキルが組み合わさった価値ある能力です。
「誰でもできること」と思っていることでも、それを継続的に、高い水準で、他の業務と両立させながら行うことは、決して容易ではありません。
掃除、整理整頓、時間管理といった基本的な事柄でさえ、それを高いレベルで実践できる人は限られています。
この無力感から抜け出すためには、まず「誰でもできる」という言葉の呪縛から自分を解放することが求められます。
他人との比較ではなく、過去の自分と比較してどれだけ成長できたか、という視点を持つことが大切です。
また、自分が当たり前だと思っているスキルが、他の人にとっては「すごいね」と評価されるものである可能性に気づくことも、無力感を克服する鍵となります。
「自分にできることは何もない」と感じる心理

「誰でもできることしかできない」という無力感がさらに進むと、「結局、自分にできることは何もない」という、より深刻な心理状態に陥ることがあります。
これは、自己肯定感が極度に低下し、自分の存在価値そのものを見失いかけている危険なサインと言えます。
このような心理に陥る大きな原因は、比較対象の設定ミスにあります。
SNSなどで目にする華やかな成功者や、自分の分野のトップランナーと自分を比較してしまうと、自分の能力や実績が取るに足らないものに思えてしまいます。
しかし、それは全く土俵の違う相手と戦おうとしているのと同じです。
また、「できる・できない」という二元論でしか自分を評価できなくなっている可能性も考えられます。
人は、スキルや能力だけで構成されているわけではありません。
誠実さ、優しさ、粘り強さといった人柄や、物事に対する姿勢も、その人の大切な価値の一部です。
しかし、「自分にできることは何もない」と感じているときは、そうした目に見えにくい自分の長所を完全に見過ごしてしまいます。
この状態から回復するには、まず「自分には価値がない」という思い込みに疑いの目を向けることが必要です。
自分ができることを紙に書き出してみると、思っていたよりも多くのことができる自分に気づくかもしれません。
その一歩を助けるために、項目に沿って「できていること」を棚卸し・記録できる自己肯定感ワークブックを使うと続けやすくなります。
「自分ができることは他人もできる」という考えの危険性

この思い込みは、単なる個人の思考のクセにとどまらず、人間関係、特に職場において深刻な問題を引き起こす可能性があります。
ここでは、その考え方がはらむ具体的な危険性について解説します。
- 「自分ができることは他人もできる」はパワハラか
- なぜ上司は「自分ができることは他人もできる」と考えるか
- 自分ができることができない人への苛立ち
- なぜ自分と同じレベルを求めるのか
- 「自分ができないことを他人に求める」のことわざ
- 健全な自信がある人の性格の特徴
- 「自分ができることは他人もできる」の総まとめ
「自分ができることは他人もできる」はパワハラか
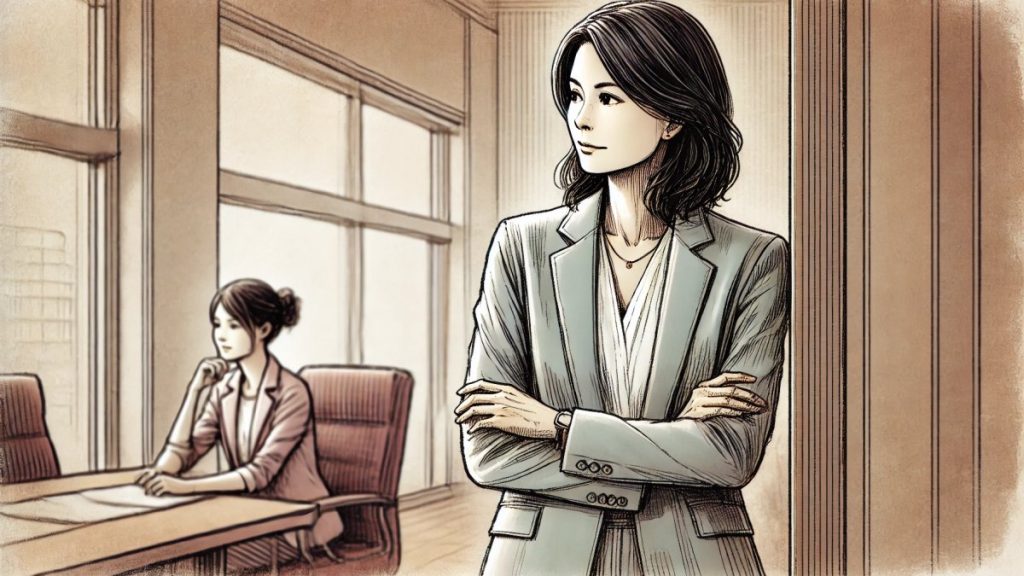
「自分ができることは他人もできるはずだ」という考え方は、特に上司と部下のような力関係が存在する場面で、パワーハラスメント(パワハラ)に直結する危険性を秘めています。
パワハラの定義の一つに、「能力や経験を大きく超える、または過小な要求をすること」が含まれており、この考え方はまさにその土壌となり得るからです。
上司が自分の成功体験やスキルを基準に、「この仕事はこれくらいの期間でできて当然だ」「これくらいのレベルの成果を出して当たり前だ」と部下に要求したとします。
しかし、部下のスキル、経験、知識、さらには現在の業務量や心身の状態は、上司とは全く異なります。
これらの個人的な背景を無視して、自分の物差しだけで過大な要求を突きつける行為は、相手を精神的に追い詰め、パワハラと認定される可能性が十分にあります。
重要なのは、要求する側に「パワハラの意図」があったかどうかではありません。
相手がその要求によって精神的な苦痛を感じ、職場環境が悪化したと判断されれば、それはパワハラになり得ます。
「指導」と「パワハラ」の境界は紙一重です。
部下を成長させたいという善意の気持ちからであっても、「自分ができるのだから、あなたもできるはず」という一方的な押し付けは、相手の成長を促すどころか、自信を喪失させ、関係を悪化させるだけの結果を招きかねません。
現行の公式指針でも、優越的関係を背景に「業務上必要かつ相当な範囲を超え」就業環境を害する言動はパワハラの要素と明記されています。
組織で心理的安全性を高め、指導とパワハラの線引きを日々のマネジメントに落とし込むなら、『恐れのない組織』が実務に役立つフレームを提供してくれるでしょう。
なぜ上司は「自分ができることは他人もできる」と考えるか
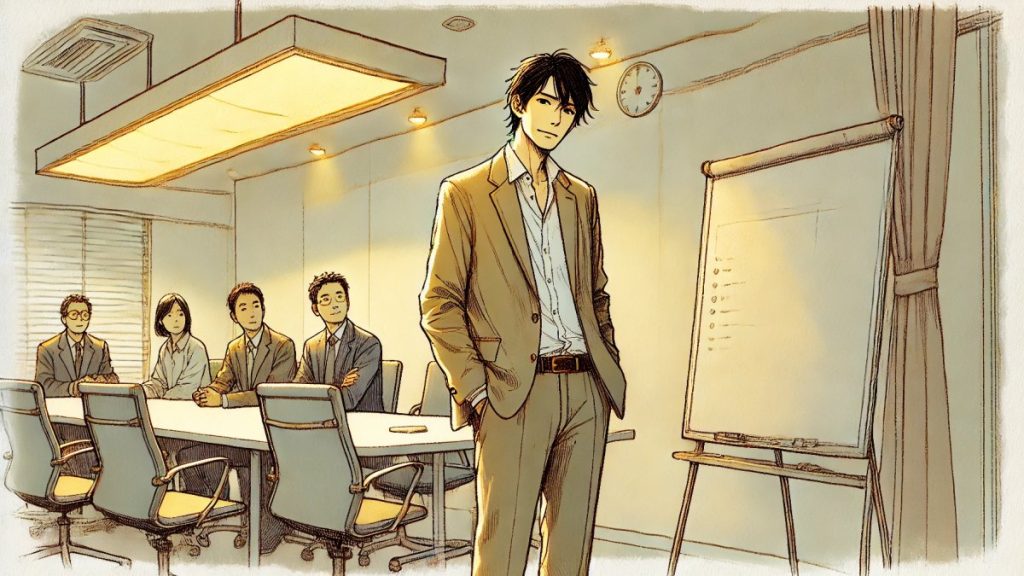
上司がこのような思考に陥る背景には、いくつかの理由が考えられます。
一つは、上司自身がその分野で高い能力を持ち、成功体験を積み重ねてきたケースです。
自分の努力で困難を乗り越えてきた経験から、「やればできる」という信念が強く、他人ができない理由を「努力不足」や「やる気のなさ」に帰結させてしまいがちです。
二つ目に、過去の自分の経験を美化、あるいは一般化してしまう傾向があります。
「自分が若い頃は、もっと大変な状況でもこれをやり遂げた」といった具合です。
しかし、時代背景、労働環境、利用できるツールなどは常に変化しており、過去の常識が現在も通用するとは限りません。
三つ目として、コミュニケーション不足が挙げられます。
上司が部下一人ひとりの能力や得意・不得意、抱えている仕事の状況を正確に把握していない場合、「おそらくできるだろう」という憶測で判断してしまいます。
部下の側も、上司からの期待に応えようとするあまり、「できません」と言えずに無理な要求を受け入れてしまうことも、この問題を助長します。
これらの理由から、上司は悪意なく部下に過度な期待をかけてしまうのです。
この思考パターンは、個人の資質だけでなく、組織内のコミュニケーション文化にも根差した問題であると言えます。
自分ができることができない人への苛立ち
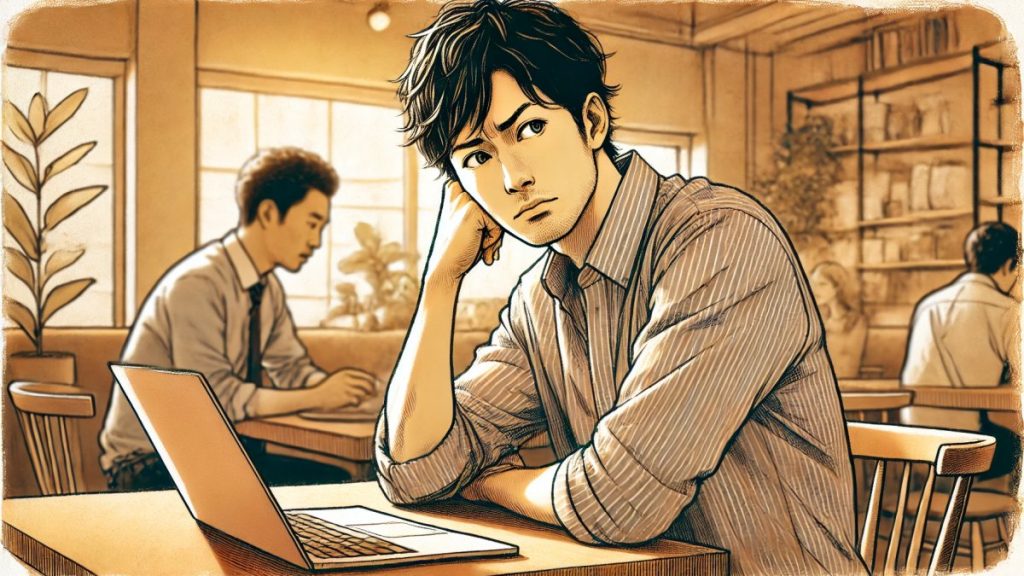
自分にとっては当たり前にできることを、目の前の人ができないでいると、なぜか強い苛立ちを感じてしまうことがあります。
この感情は、単に「非効率だ」と感じるだけでなく、もっと複雑な心理が絡み合っています。
まず考えられるのは、「自分の価値観や常識が否定された」という感覚です。
自分が正しいと信じているやり方や、当たり前だと思っている基準が通用しない状況に直面すると、人は不安や不快感を覚えます。
その感情が、相手への苛立ちとして表出するのです。
また、相手をコントロールしたいという無意識の欲求が関係している場合もあります。
「相手に自分の思い通りに動いてほしい」「自分の期待に応えてほしい」という気持ちが強いほど、期待が裏切られたときの失望感や怒りは大きくなります。
これは、相手を独立した一人の人間として尊重するのではなく、自分の延長線上にある存在として捉えてしまっている証拠かもしれません。
さらに、自分自身がそのスキルを習得するために費やした努力を、無意識のうちに相手にも求めている可能性もあります。
「自分はこれだけ苦労してできるようになったのだから、あなたも同じように苦労すべきだ」という、ある種の代償を求める心理が働くのです。
この苛立ちは、相手の能力不足そのものよりも、自分の内面にある期待や価値観が生み出している感情であることを理解することが重要です。

なぜ自分と同じレベルを求めるのか
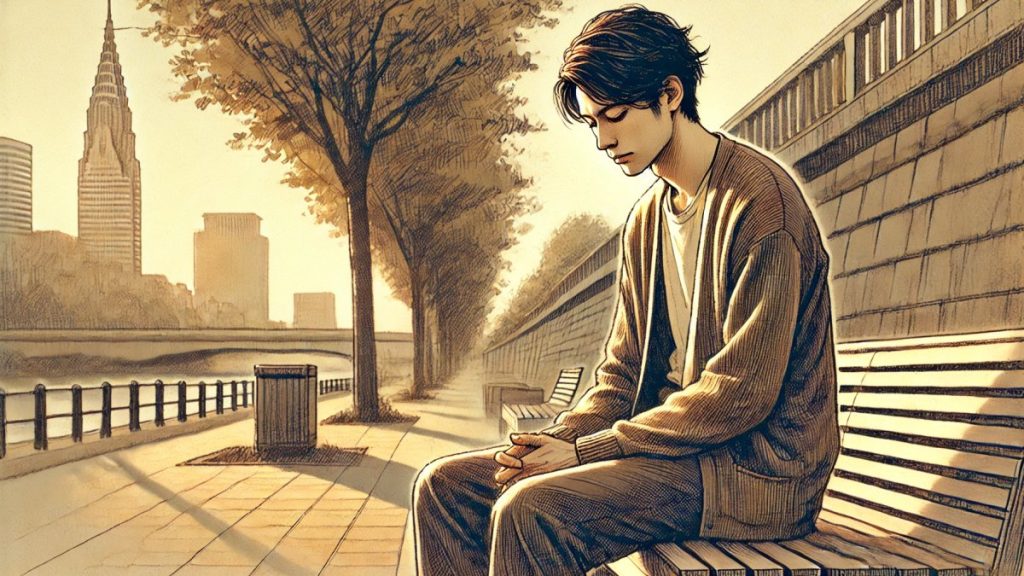
私たちは、なぜ他人に対して自分と同じレベルの能力や行動を求めてしまうのでしょうか。
その根底には、「自分と同じであってほしい」という、人間の根源的な欲求が存在します。
自分と考え方や能力が似ている人と一緒にいると、人は安心感を覚え、物事がスムーズに進むと期待するからです。
これは、集団の同質性を保とうとする本能的な働きとも言えます。
異なる意見や能力を持つ人がいると、それを理解し、調整するために余分なエネルギーが必要になります。
そのため、無意識のうちに、自分と同じような人を求め、異なる人を排除しようとする心理が働くことがあります。
ビジネスの文脈では、効率性の追求がこの傾向を加速させます。
チーム全員が同じレベルのスキルを持っていれば、業務の指示や分担が容易になり、生産性が上がると考えがちです。
しかし、これは短期的な視点に過ぎません。
長期的に見れば、異なるスキルや視点を持つ多様な人材がいる組織の方が、変化に対応しやすく、革新的であることは多くの研究で示されています。
自分と同じレベルを他人に求めることは、一見すると合理的に思えるかもしれませんが、実際には他者の個性や成長の可能性を否定し、人間関係に不要な緊張感をもたらす行為です。
自分と他人の「違い」を、脅威ではなく、価値として捉え直す視点が求められます。
「自分ができないことを他人に求める」のことわざ

これまで「自分ができることは他人もできる」という思い込みについて考えてきましたが、興味深いことに、日本語にはその真逆の状況を戒めることわざも存在します。
例えば、「人に高きを望むな、おのれの高からざることを知れ」という言葉があります。
これは、自分自身が大して優れていないことを自覚し、他人に過剰な期待をすべきではない、という意味です。
このことわざは、自己客観視の重要性を教えてくれます。
私たちは、自分のことは棚に上げて、他人に対しては理想的な姿を求めてしまいがちです。
「上司はもっとリーダーシップを発揮すべきだ」「部下はもっと主体的に動くべきだ」といった要求は、果たして自分自身が完璧にできていることでしょうか。
「自分ができることは他人もできる」という思い込みも、「自分ができないことを他人に求める」という傲慢さも、根は同じです。
どちらも、自分というフィルターを通してしか他人を見ることができず、相手の状況や能力をありのままに捉えられていないという点で共通しています。
これらのことわざに触れることは、自分の思考のクセを相対化する良い機会となります。
常に自分を客観視し、「自分はどうか?」と問いかける姿勢を持つことが、他者への過度な期待や要求を減らし、より良い関係を築く上で不可欠です。
健全な自信がある人の性格の特徴
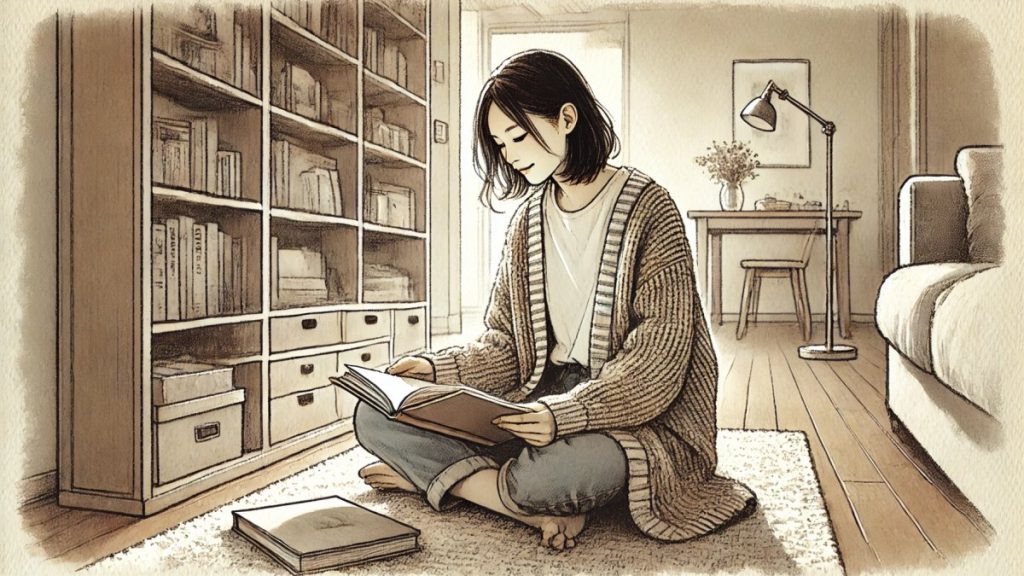
では、他者に対して過度な要求をせず、自分自身の価値も正しく認められる「健全な自信」を持つ人には、どのような特徴があるのでしょうか。
彼らの思考や行動パターンを知ることは、私たちが目指すべき姿を明確にする上で役立ちます。
健全な自信を持つ人は、まず、自分の価値を他者との比較で測りません。
彼らの関心は、他人に勝つことではなく、昨日の自分より成長することに向けられています。
そのため、他人の成功を妬んだり、他人の失敗を喜んだりすることがなく、素直に称賛し、手を差し伸べることができます。
次に、彼らは自分の得意なことと不得意なことを客観的に理解しています。
これを「自己受容」と言います。
不得意なことがあっても、それを自分の価値の欠如とは結びつけず、「これは苦手だから、得意な人にお願いしよう」と合理的に判断できます。
この姿勢が、他人の能力を尊重することにも繋がります。
以下の表は、「自己肯定感が低い人の思考」と「健全な自信がある人の思考」を比較したものです。
| 状況 | 自己肯定感が低い人の思考 | 健全な自信がある人の思考 |
|---|---|---|
| 仕事で成功した時 | 「まぐれだ」「誰でもできることだ」 | 「自分の努力が実った」「嬉しい」 |
| 仕事で失敗した時 | 「自分はなんてダメなんだ」 | 「なぜ失敗したのか分析し、次に活かそう」 |
| 他人が成功した時 | 「それに比べて自分は…」と落ち込む | 「すごい!おめでとう!」と素直に喜ぶ |
| 他人が助けを求めてきた時 | 「迷惑だ」「なぜ自分でできないんだ」 | 「どうしたの?手伝えることはある?」 |
| 新しい挑戦をする時 | 「失敗したらどうしよう」とためらう | 「面白そう!まずはやってみよう」 |
このように、健全な自信がある人は、物事の結果に一喜一憂するのではなく、プロセスや成長を大切にします。
そして、自分をありのままに受け入れているからこそ、他人もありのままに受け入れることができるのです。

「自分ができることは他人もできる」の総まとめ

この記事を通じて、「自分ができることは他人もできる」という思い込みが、いかに複雑な心理的背景を持ち、人間関係に様々な影響を及ぼすかを見てきました。
最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- 「自分ができることは他人もできる」は認知バイアスの一種
- 自分の物差しで他人を測る行為は誤解や対立を生む
- 自己肯定感の低さが自分の能力の過小評価に繋がる
- 「これくらいできるはず」という期待は相手への圧力になり得る
- 上司の思い込みはパワハラと受け取られるリスクがある
- 他者への苛立ちは自分の内面にある期待や価値観が原因
- 自分と他人は能力も背景も違って当たり前
- 自分を大切にすることが他者理解の第一歩となる
- 無力感は他者との不必要な比較から生まれることが多い
- 自分の価値は「できること」の数や種類だけで決まらない
- 客観的な視点で自分と他人を見る努力が大切
- 相手の能力や状況を尊重し、理解しようと努める姿勢
- 健全な自信は自己受容から育まれる
- 自分の得意・不得意を正しく把握することが重要
- 期待値のズレは率直なコミュニケーションで解消する