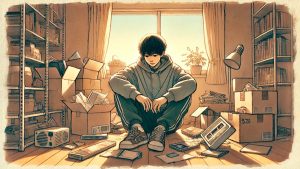「自分だけいつも残業している…」と感じることはありませんか。
周りを見渡すと、いつも残業している人は特定の人に偏りがちです。
その特徴として、仕事ができない、あるいは無能だと自分で感じてしまうケースもあれば、逆に優秀な人だからこそ多くの業務が集中してしまうケースもあります。
新人なのに1人で残業を続けていたり、課長や部長など上司だけが深夜まで残っていたり、または自分の部署だけ残業が常態化しているなど、その状況は様々でしょう。
このような一人に負担が偏る状態は、時にパワハラではないかと疑問に思うかもしれません。
そもそも、残業が多すぎる原因は何なのでしょうか。
法的に残業が多すぎなのは何時間からで、例えば月の残業25時間はホワイト企業といえるのか、それとも月の残業60時間は心身に危険が及ぶ水準なのか、客観的な基準も気になるところです。
この記事では、会社が一人だけ残業させないための対策を含め、「一人だけ残業が多い」という問題の根本原因から具体的な解決策までを詳しく解説していきます。
- 一人だけ残業が多くなる具体的な原因と特徴
- 残業時間の適正レベルや危険な水準
- 会社組織として残業を減らすための視点
- 残業状況を改善するための具体的な対処法
一人だけ残業が多いのはなぜ?その原因と特徴

- そもそも残業が多すぎる原因は?
- いつも残業している人の持つ特徴
- 仕事ができない、無能と見なされる傾向
- 優秀な人だからこそ仕事が集中する
- 一人に負担が偏るのはパワハラか
- 自分の部署だけ残業の場合
そもそも残業が多すぎる原因は?

特定の人だけ残業が多くなる背景には、個人の問題と組織の問題が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
まず結論として、残業が常態化する主な原因は、「個人の仕事の進め方」と「組織の体制や文化」の2つに大別できます。
理由として、個人のスキルや性格が仕事の処理速度に影響を与える一方で、会社全体の業務量や人員配置、評価制度といった組織的な要因が、個人の努力だけでは解決できない状況を生み出しているからです。
具体的には、個人の原因としては、業務に必要なスキルが不足している、効率的な段取りが苦手、あるいは他者からの依頼を断れない性格などが挙げられます。
一方で、組織的な原因としては、慢性的な人手不足、特定の個人に業務が偏る不適切な業務分担、残業を美徳とする古い企業文化、さらには上司のマネジメント能力の欠如などが考えられるでしょう。
このように、残業問題は単一面からではなく、個人と組織双方の視点から原因を分析することが、解決への第一歩となります。
いつも残業している人の持つ特徴

いつも残業している人には、いくつかの共通した特徴が見られます。
もしご自身や周りの人が当てはまる場合は、それが残業の根本原因となっているかもしれません。
主に、以下の4つの特徴が挙げられます。
- 能力・スキルが業務レベルに追いついていない
単純に、与えられた仕事を勤務時間内に終えるためのスキルや知識が不足しているケースです。この場合、他の人と同じ量の仕事でも時間がかかってしまい、結果的に残業せざるを得なくなります。 - 仕事量に明らかな個人差がある
本人の能力とは関係なく、なぜかその人にだけ大量の仕事が割り振られている状態です。前任者が辞めた業務をそのまま引き継いだり、上司が管理しきれずに仕事を丸投げしたりすることで発生します。 - 責任感が強く、頼まれた仕事を断れない
優しい性格や強い責任感から、自分の仕事が終わっていなくても同僚や上司からの依頼を引き受けてしまうタイプです。結果として自分のキャパシティを超え、毎日残業することになります。 - チームや部署全体の業務量が多すぎる
個人ではなく、チーム全体が人員不足や過大な業務量を抱えているケースです。この場合、「みんなで残業するのが当たり前」という雰囲気になり、一人だけ定時で帰ることに罪悪感を覚えてしまいます。
これらの特徴は一つだけでなく、複数が絡み合っていることも少なくありません。
ご自身の状況がどのパターンに近いかを客観的に把握することが重要です。
仕事ができない、無能と見なされる傾向

「仕事ができない」「要領が悪い」といった自己評価が、残業の直接的な原因になっているケースは少なくありません。
この傾向がある人は、定時内に仕事を終わらせる能力が不足しているため、必然的に残業でカバーすることになります。
周囲が定時で帰宅していく中で自分だけが残業していると、さらに「自分は無能だ」というネガティブな感情を強めてしまう悪循環に陥りがちです。
具体的には、以下のようなスキル不足が考えられます。
- PCスキルの不足
ショートカットキーを知らない、タイピングが遅いなど、基本的な操作に時間がかかっている。 - 情報整理能力の欠如
どの仕事から手をつけるべきか優先順位を決められず、場当たり的に作業を進めてしまう。 - コミュニケーション不足
分からないことをすぐに質問できず、一人で抱え込んで時間を浪費してしまう。
ただし、これらのスキルは学習や訓練によって改善できるものがほとんどです。
自分に何が足りないのかを正確に把握し、自己研鑽の時間を作ることが、残業を減らすための有効な手段となり得ます。
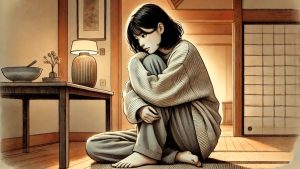
優秀な人だからこそ仕事が集中する

意外に思われるかもしれませんが、「優秀な人」であることも、一人だけ残業が多くなる大きな原因の一つです。
なぜなら、上司や同僚は「あの人に任せれば安心だ」「仕事が早くて質も高い」と判断し、難易度の高い仕事や重要な業務を次々と依頼するからです。
優秀な人自身も、期待に応えようとする責任感から、それらの仕事を安易に引き受けてしまう傾向があります。
その結果、個人の処理能力をはるかに超える仕事量となり、物理的に残業しなければ終わらない状況が生まれます。
この状況には、いくつかのデメリットが潜んでいます。
- バーンアウト(燃え尽き症候群)のリスク
過度な業務負担とプレッシャーが続くと、心身ともに疲弊し、仕事への意欲を失ってしまう可能性があります。 - スキルの偏り
特定の業務に特化しすぎることで、他のスキルを伸ばす機会を失うことがあります。 - 組織の成長停滞
特定の個人に依存する体制は、その人がいなくなった場合に業務が停滞するリスクを抱えており、組織全体の成長を阻害します。
優秀であることは素晴らしいことですが、それによって心身の健康を損なっては元も子もありません。
自分の限界を認識し、時には仕事を断る勇気も必要です。

一人に負担が偏るのはパワハラか

特定の従業員一人に業務負担が極端に偏る状況は、場合によってはパワーハラスメント(パワハラ)に該当する可能性があります。
パワハラかどうかを判断する際には、厚生労働省が示す3つの要素をすべて満たしているかを確認する必要があります。
この定義は「優越的な関係」「業務上必要かつ相当な範囲を超える」「就業環境が害される」の3点で整理されています。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
上司から部下への指示など、職務上の地位や人間関係で逆らったり断ったりすることが難しい関係性の中で行われること。 - 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がない、またはそのやり方が不適切であること。一人の従業員にだけ、遂行不可能な量の業務を押し付けることはこれに該当する可能性があります。 - 労働者の就業環境が害されること
その言動によって従業員が身体的または精神的に苦痛を感じ、働く上で見過ごせないほどの支障が生じること。過度な残業による心身の不調などがこれにあたります。
もし「他の同僚と比べて明らかに過大な業務を強制されている」「断ると不利益な扱いを受ける」といった状況であれば、パワハラの可能性が考えられます。
このような場合は、社内の相談窓口や労働組合、または外部の専門機関である総合労働相談コーナーなどに相談することを検討しましょう。
自分の部署だけ残業の場合

自分だけでなく、部署のメンバーのほとんどが残業している、あるいは上司だけがいつも遅くまで残っているという状況は、個人ではなく組織構造に問題があるサインです。
この場合、原因は部署全体の業務量が、所属する人員のキャパシティを恒常的に超えていることにあります。
特に、ギリギリの人数で業務を回している会社では、一人が欠けるだけで部署全体の業務が破綻しかねず、結果として全員で残業してカバーする文化が根付いてしまいます。
マネジメントの問題点
上司が部下の業務進捗や負荷を適切に管理できていない、いわゆるマネジメント不全も大きな原因です。
本来であれば、マネージャーは他部署と交渉して業務量を調整したり、チーム内での優先順位を決めて「やらないこと」を判断したりする役割を担っています。
この機能が働いていない部署では、仕事が際限なく増え続け、現場のメンバーが疲弊してしまいます。
上司自身がプレイングマネージャーとして自分の業務に忙殺され、管理業務にまで手が回っていないケースも少なくありません。
このような組織的な問題は、一個人の力だけで解決するのは困難です。
部署全体で問題意識を共有し、マネージャーを通じて会社上層部に業務分担の見直しや人員の増強を働きかける必要があります。
一人だけ残業が多い状況を改善するための視点

- 残業が多すぎなのは何時間から?60時間は?
- 月の残業25時間はホワイト企業といえるか
- 会社が一人だけ残業させないための対策
- 新人が1人で残業することの危険性
- 一人だけ残業が多いと感じた時の対処法
残業が多すぎなのは何時間から?60時間は?

残業時間の過多を判断する上で、法律上の基準を知っておくことは非常に重要です。
労働基準法では、時間外労働(残業)の上限が定められています。
この基準となるのが「36協定(さぶろくきょうてい)」です。
36協定を締結している場合でも、残業時間には以下の通り上限が設けられています。
| 項目 | 上限時間 |
|---|---|
| 原則 | 月45時間、年360時間 |
| 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項付き36協定) | ・年720時間以内 ・複数月平均80時間以内(休日労働含む) ・月100時間未満(休日労働含む) ・月45時間を超えられるのは年6ヶ月まで |
現行の上限規制は上記表のとおりで、違反時は罰則の対象となることがあります。
月の残業が45時間を超える状態が常態化している場合は、法律違反の可能性があります。
過労死ラインと月60時間の危険性
特に注意すべきは、心身の健康への影響です。
厚生労働省は、脳・心臓疾患のリスクが高まる時間外労働の基準として、いわゆる「過労死ライン」を提示しています。
- 発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働
- 発症前2~6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働
これらは、労災認定の専門検討会報告書で示された考え方に基づく水準です。
この基準に照らし合わせると、月の残業が60時間に達している状態は、過労死ラインに近づきつつある非常に危険な水準であると理解できます。
健康を害する前に、業務量の調整や働き方の見直しが急務と言えるでしょう。
月の残業25時間はホワイト企業といえるか

月の残業時間が25時間という水準は、法的な観点から見れば全く問題ありません。
前述の通り、36協定における残業時間の上限は原則月45時間であり、25時間はその範囲内に十分に収まっています。
しかし、「ホワイト企業」と感じるかどうかは、個人の価値観や労働環境によって大きく異なります。
残業25時間をどう捉えるか
一般的に、月の実働日数を20日と仮定すると、残業25時間は1日あたり1時間強の残業に相当します。
これを「毎日少し残業がある」と捉えるか、「その程度なら許容範囲」と捉えるかで評価は分かれるでしょう。
- ホワイトと捉える見方
繁忙期などを考慮すれば、平均してこの程度の残業は十分に考えられる範囲。全く残業がない会社の方が珍しく、むしろ健全な経営状況と見ることもできます。 - グレー(またはブラック)と捉える見方
プライベートの時間を最優先したい人にとっては、毎日1時間の残業でも苦痛に感じる可能性があります。また、基本給が低く、残業代で生計を立てる構造になっている場合は、決して「ホワイト」とは言えません。
結論として、残業25時間という数字だけでホワイト企業かどうかを断定することは困難です。
給与水準や有給休暇の取得率、職場の雰囲気といった他の要素と合わせて総合的に判断する必要があります。
会社が一人だけ残業させないための取り組み

特定の個人に残業が集中する状況を防ぐためには、会社組織として体系的な取り組みを行うことが不可欠です。
企業が実施すべき主な対策は、以下の通りです。
- 業務の可視化と標準化
まず、誰がどのような仕事にどれくらいの時間をかけているのかを正確に把握します。業務内容を可視化することで、特定の個人にかかっている負荷が明確になります。その上で、業務マニュアルを作成するなどして作業を標準化し、誰でも代替可能な体制を整えることが重要です。 - 客観的な基準に基づく業務分担
個人の能力や経験を考慮しつつも、客観的なデータに基づいて公平に業務を再配分します。上司の感覚や「この人なら大丈夫だろう」といった曖昧な理由で仕事を振るのをやめ、チーム全体で負荷を平準化する意識を持つことが求められます。 - 勤怠管理の徹底と上司への指導
タイムカードやPCのログオン・ログオフ時間など、客観的なデータで労働時間を管理します。残業が多い従業員や部署が確認された場合、その上司に対して原因の分析と改善策の提出を求めるなど、管理職への指導を徹底します。 - 評価制度の見直し
「残業している人=頑張っている人」という評価をやめ、労働時間の長さではなく、時間内にどれだけの成果を出したかを評価する制度へと転換します。これにより、効率的に働くことへのインセンティブが生まれます。
「やらないこと」を決めて業務集中を促す基礎づくりには、シンプルな選択基準を学べる解説書が有効です。
これらの取り組みは、従業員の健康を守るだけでなく、生産性の向上や離職率の低下にも繋がり、企業にとって長期的な利益となります。
新人が1人で残業することの危険性

特に社会人経験の浅い新人が一人で残業する状況は、様々なリスクをはらんでおり、企業は安全配慮義務の観点からこれを避けさせるべきです。
新人が一人で残業することには、主に以下の3つの危険性が伴います。
- 心身の健康を損なうリスク
新人はまだ業務に慣れておらず、精神的なプレッシャーを感じやすい状態にあります。一人で長時間労働を続けることで、うつ病などのメンタルヘルス不調や、最悪の場合、過労による突然死に至る危険性も否定できません。周りに相談できる人がいない孤独な環境は、そのリスクをさらに高めます。 - 業務上の重大なミスを誘発するリスク
経験不足の新人が自己判断で業務を進めると、大きなミスに繋がる可能性があります。周りに確認や相談ができる先輩社員がいないため、誤った判断をしてしまったり、トラブルの発見が遅れたりすることが考えられます。 - 防犯・安全上のリスク
深夜のオフィスに一人でいることは、防犯上の観点からも危険です。特に女性社員の場合は、通勤時の安全確保も問題となります。また、オフィス内で急な体調不良や事故が発生した際に、誰も気づいてあげられないというリスクもあります。
企業としては、部下の残業を許可制にし、特に新人に対しては一人での残業を原則禁止とするなど、明確なルールを設けて運用することが強く求められます。
一人だけ残業が多いと感じた時の対処法

一人だけ残業が多い状況は、心身に大きな負担をかけ、仕事のパフォーマンスを低下させます。
もしあなたがこの状況に陥っていると感じたら、問題を放置せず、積極的に行動を起こすことが大切です。
この記事で解説した内容を基に、具体的な対処法をまとめました。
- まず自分の残業がどのパターンに当てはまるか分析する
- 能力不足が原因なら自己研鑽の時間を確保する
- 仕事が集中しているなら自分のキャパシティを上司に伝える
- 責任感が強すぎるなら「断る勇気」を持つ意識を持つ
- 会社の組織的な問題が原因である可能性を疑う
- 労働基準法における残業時間の上限(月45時間)を把握する
- 月60時間以上の残業は過労死ラインに近い危険な水準と認識する
- 業務の偏りがパワハラに該当しないか3つの要素で確認する
- 客観的な勤怠記録や業務内容のメモを取っておく
- 具体的なデータを持って上司に業務分担の見直しを相談する
- 一人で抱え込まず、信頼できる同僚に協力を求める
- 会社の相談窓口や労働組合に現状を伝える
- 心身に不調を感じたら迷わず医師の診断を受ける
- 状況が改善されない場合は転職も有力な選択肢と考える
- 外部の労働相談機関を活用することも検討する