あなたの周りに、言い訳ばかりする人はいないでしょうか。
その人の特徴的な口癖や話し方、言い訳ばかりの性格に悩んでいるかもしれません。
特に職場で仕事ができないと感じさせる態度には、具体的な対処法が知りたいと思うものです。
この記事では、言い訳ばかりする人の育ちと心理の関係を深く掘り下げ、その原因と直し方、さらには放置した場合の悲惨な末路を避けるために注意するべき点まで網羅的に解説します。
また、女性に見られる傾向や、もしかしたらその行動が病気のサインかもしれない可能性についても触れていきます。
言い訳ばかりする人にならないため気を付けるべきことも紹介しますので、他者との関わり方だけでなく、自分自身を振り返るきっかけとしてお役立てください。
- 言い訳ばかりする人の育ちに見られる共通点
- 行動の裏にある心理や性格的な特徴
- 職場での具体的な対処法と付き合い方
- 言い訳癖を改善するための具体的な直し方
言い訳ばかりする人の育ちと心理的特徴

- 言い訳ばかりする人の心理と特徴
- 女性に多い性格
- 特有の口癖や話し方のパターン
- 病気のサインかもしれない可能性
- 原因と自分での直し方
言い訳ばかりする人の心理と特徴
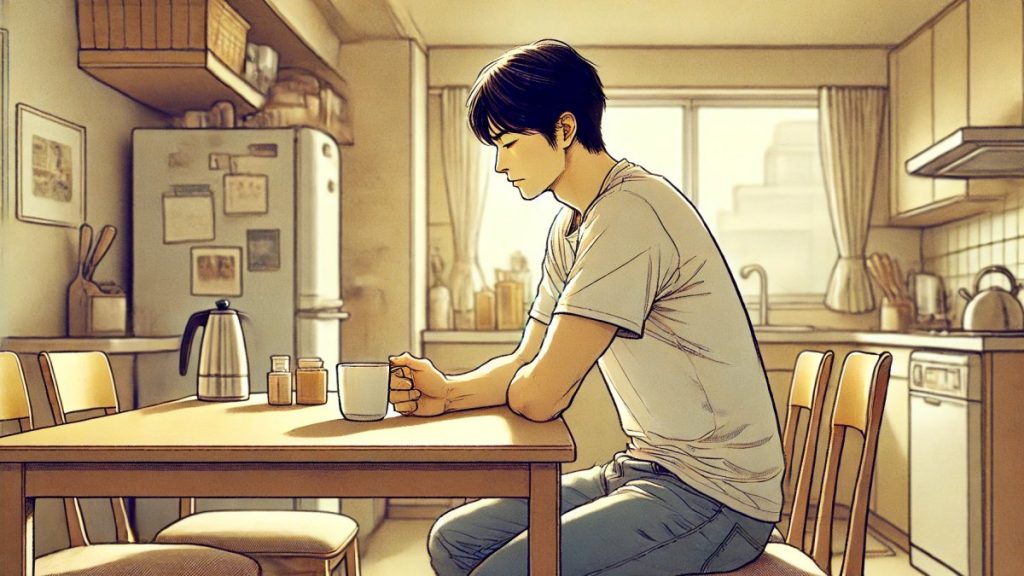
言い訳ばかりする人の行動の根底には、自分を守りたいという強い自己防衛本能があります。
失敗を他人に指摘されたり、責任を追及されたりすることに対して、過度な恐怖を感じる傾向です。
これは、自分の価値が下がってしまう、あるいは他者からの評価を失ってしまうという不安に直結します。
この心理の背景には、低い自己肯定感や、他人から認められたいという承認欲求が隠れていることが多いです。
自分に自信がないため、ありのままの自分では認められないと思い込み、失敗や欠点を隠すために言い訳という手段を選んでしまいます。
また、失敗そのものへの強い恐怖心も大きな特徴です。
過去に失敗を厳しく責められた経験がトラウマになっていたり、完璧でなければならないというプレッシャーを感じていたりすると、失敗を認めることができなくなります。
結果として、自分は悪くないと正当化するために、無意識に言い訳をしてしまうのです。
女性に多い性格

言い訳をする行動に性別で明確な差があるわけではありませんが、一部で女性に多いとされる性格傾向が、言い訳に結びつくことがあります。
一般的に、女性は男性に比べて共感性や協調性を重んじる傾向があるとされています。
このため、周囲との和を乱すことを恐れたり、相手の期待に応えなければならないというプレッシャーを感じやすかったりします。
このような状況下で失敗をした場合、関係性を壊したくないという思いから、自分を正当化するための言い訳が出やすくなることがあります。
自分の非を直接的に認めることが、相手を失望させたり、場の雰囲気を悪くしたりするのではないかと不安に感じるのです。
もちろん、これはあくまで一面的な傾向に過ぎません。
個人の性格や育った環境が大きく影響するため、すべての女性に当てはまるわけではないことを理解しておく必要があります。
特有の口癖や話し方のパターン

言い訳ばかりする人には、会話の中に共通した口癖や話し方のパターンが見られます。
これらの表現は、無意識のうちに責任を回避し、自分を守るために使われることが多いです.
代表的な口癖としては、「でも」「だって」「〇〇のせいで」といった責任転嫁の言葉が挙げられます。
また、「時間がなくて」や「知らなかった」のように、外的要因や情報不足を理由にするケースも少なくありません。
国内の研究結果によると、仕事・学習場面で「時間がない」等の言い訳を先に考えてしまうと、学習量の低下や評価の不利に影響するとされています。
話し方としては、結論を先延ばしにしたり、話を曖昧にぼかしたりする傾向があります。
質問に対して直接答えず、関係のない別の話題にすり替えようとすることもあります。
これは、問題の核心に触れるのを避け、追及から逃れようとする心理の表れです。
以下に、代表的な口癖と、その裏にある心理をまとめました。
| 口癖・言い回し | その裏にある心理 |
|---|---|
| 「でも」「だって」 | 相手の意見を否定し、自分の正当性を主張したい |
| 「時間がなかった」 | 計画性のなさを隠し、外的要因のせいにしたい |
| 「そんなつもりじゃなかった」 | 結果ではなく意図を汲んでほしい、責任を軽くしたい |
| 「誰だってそうする」 | 自分の行動を一般化し、非を認めなくない |
病気のサインかもしれない可能性
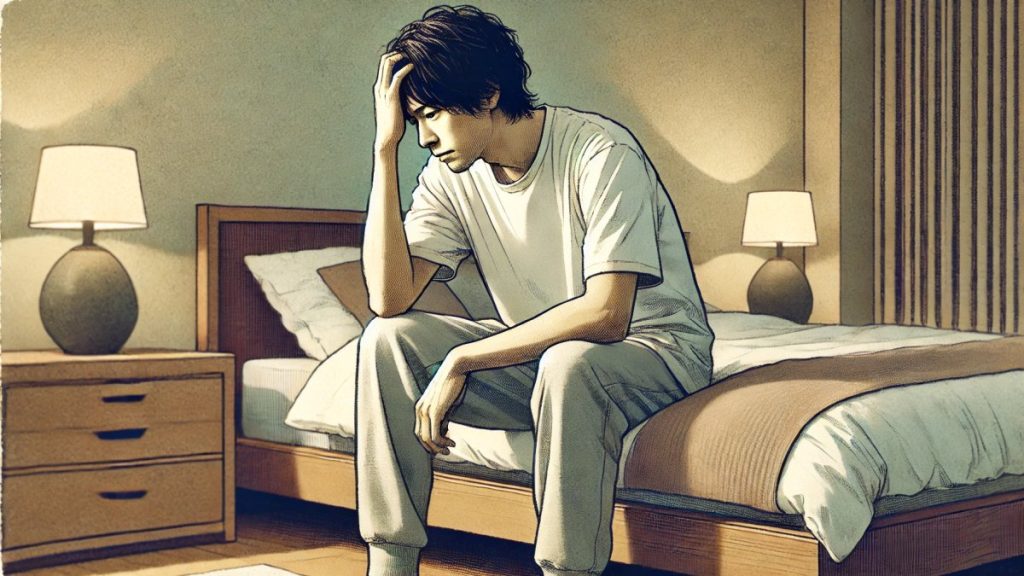
言い訳が極端に多い場合、その背景に何らかの精神的な不調や発達上の特性が隠れている可能性も指摘されています。
ただし、これは専門家による慎重な判断が必要であり、安易に「病気だ」と決めつけるべきではありません。
可能性として考えられるものの一つに、パーソナリティ障害があります。
特に、自己愛性パーソナリティ障害の傾向がある場合、自分の非を認めることが極端に難しく、他者を責めることで自己評価を維持しようとすることがあります。
また、ADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害の特性が関係しているケースも考えられます。
計画性の欠如や衝動性からミスが多くなり、それを隠すために後付けで言い訳をしてしまう、というパターンです。
国の情報サイト「発達障害ナビポータル」でも、ADHDの主な特性である「不注意や衝動性」によって、日常生活でのミスが増えやすくなる、と解説されています。
この場合、本人に悪気はなく、脳の特性によるものと理解する必要があります。
もし、本人や周囲が社会生活に深刻な支障を感じている場合は、医療機関や専門のカウンセラーに相談することが重要です。
自己判断はせず、専門家の助けを求めることをお勧めします。
原因と自分での直し方

言い訳ばかりする行動の根本的な原因は、多くの場合、幼少期の家庭環境や育ちにあります。
例えば、以下のような環境が影響を与えることがあります。
- 過干渉な親
親がすべてを決め、子ども自身が選択する機会がなかった。 - 完璧主義な家庭
少しの失敗も許されず、常に高い成果を求められた。 - 厳しい批判
失敗するたびに厳しく叱責され、自己肯定感が育たなかった。
これらの環境で育つと、失敗を過度に恐れたり、自分の判断に自信が持てなくなったりするため、自己防衛として言い訳をする癖がついてしまいます。
親の自信や子どもへの接し方は、子どもの自立心を育てたり、気分の落ち込みを防いだりすることに大きく影響します。
そのため、日頃からお子さんを認め、ポジティブに関わってあげることが大切だと言われています。
この癖を自分で直すためには、まず失敗を素直に認める勇気を持つことが第一歩です。
失敗は成長の機会であると捉え直し、「次はどうすればうまくいくか」という未来志向の考え方に切り替えることが大切です。
具体的な改善ステップ
- 自己分析
まず自分がどんな時に言い訳をするか、客観的に振り返ります。 - 事実の受容
言い訳をせず、「〇〇が原因で失敗しました」と事実を口に出す練習をします。 - 改善策の提示
失敗を認めた上で、「次は〇〇のように改善します」と具体的な対策をセットで伝える習慣をつけます。 - 他責にしない
「〇〇のせい」という考え方をやめ、常に「自分にできることは何か」を考えるように意識を変えていきます。

言い訳ばかりする人の育ちと影響

- 仕事ができない人の職場での振る舞い
- 待ち受ける悲惨な末路とは
- 周囲ができる効果的な対処法
- 言い訳する人へ注意すること
- 言い訳ばかりにならないためには?
- まとめ:言い訳ばかりする人の育ちを理解する
仕事ができない人の職場での振る舞い
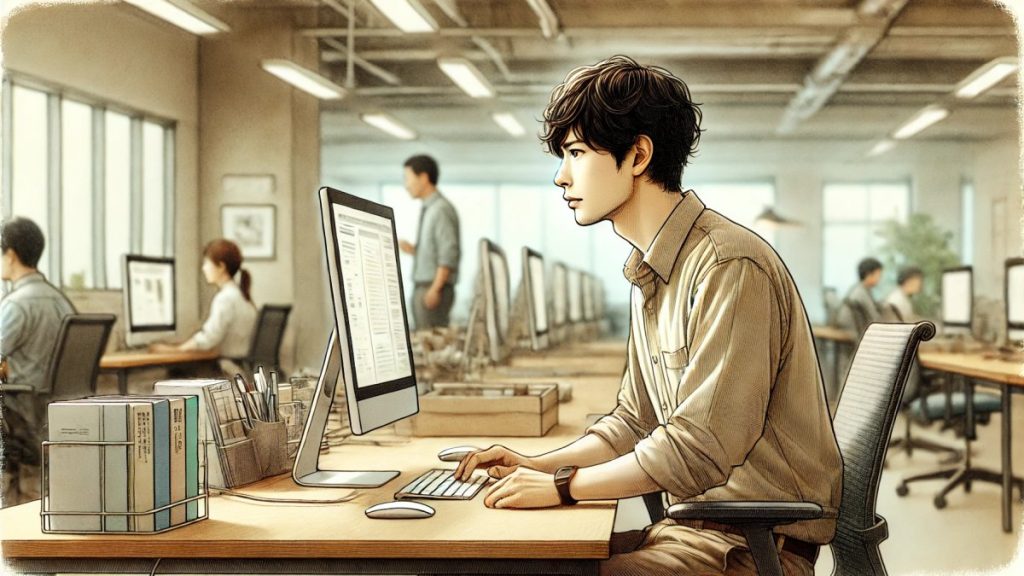
言い訳ばかりする人は、職場で「仕事ができない」という評価を受けやすくなります。
なぜなら、その行動がチームの生産性や信頼関係に悪影響を与えるからです。
最も顕著な振る舞いは、責任転嫁です。
ミスが発生した際に、「〇〇さんの指示が曖昧だった」「聞いていなかった」など、原因を自分以外の誰かや環境のせいにします。
これにより、問題の根本的な解決が遅れるだけでなく、周囲のメンバーのモチベーションを著しく低下させます。
また、報告・連絡・相談が遅れる傾向も見られます。
失敗を隠そうとするため、問題が小さいうちに報告できず、事態が悪化してから発覚するケースが少なくありません。
これは、プロジェクト全体に大きな損害を与えるリスクをはらんでいます。
このような振る舞いは、主体性や当事者意識の欠如と見なされます。
結果として、重要な仕事を任されなくなり、成長の機会を自ら失ってしまうことになります。
待ち受ける悲惨な末路とは
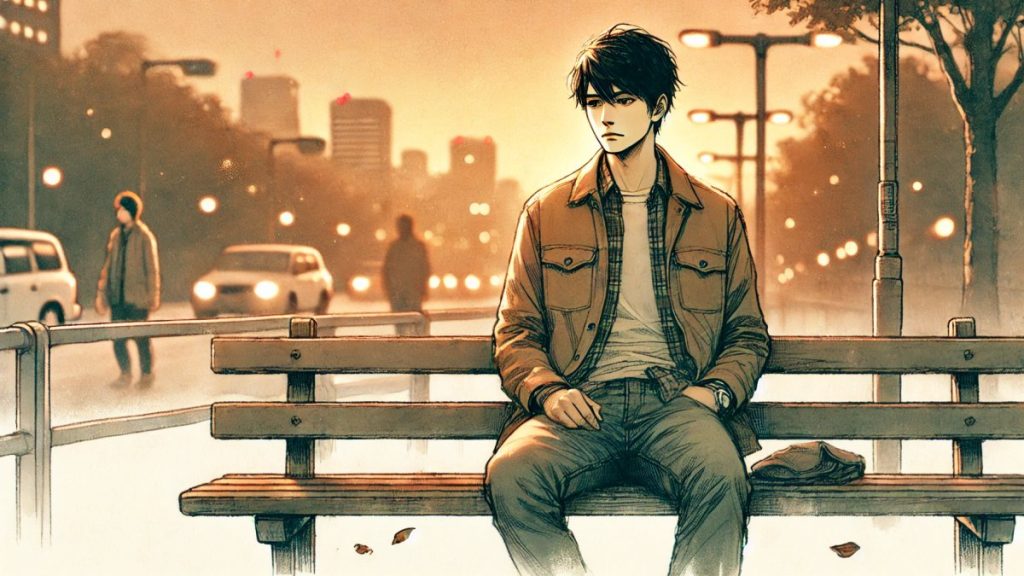
言い訳ばかりする習慣を続けた場合、その人を待ち受けるのは決して明るい未来ではありません。
短期的にはその場をしのげるかもしれませんが、長期的には深刻な事態を招く可能性があります。
最大の代償は、周囲からの信頼を完全に失うことです。
最初は多めに見てくれていた同僚や上司も、繰り返される言い訳にうんざりし、次第に距離を置くようになります。
結果として、職場内で孤立し、必要な協力が得られなくなってしまいます。
信頼を失うと、キャリアにも大きな影響が出ます。
昇進や昇給の機会は巡ってこなくなり、重要なプロジェクトからも外されるでしょう。
スキルアップの機会も減り、同僚との差は開く一方です。
最悪の場合、居場所がなくなり、退職に追い込まれるという悲惨な末路も十分に考えられます。
プライベートにおいても、友人やパートナーとの関係が悪化する原因となります。
信頼できない人と深い関係を築くのは難しく、最終的には孤独な状況に陥ってしまうリスクが高まります。
周囲ができる効果的な対処法

言い訳ばかりする人と職場で関わる際には、感情的にならず、冷静かつ建設的なアプローチを心がけることが重要です。
まず、相手が言い訳を始めたら、それを責めずに最後まで話を聞く姿勢を見せます。
高圧的な態度を取ると、相手はさらに防御的になり、かえって言い訳を重ねるだけです。
話を聞いた上で、「具体的にはどういう状況だったの?」と事実確認を促すのが効果的です。
感情論や曖昧な弁解ではなく、客観的な事実に焦点を当てることで、問題の本質が見えやすくなります。
『伝え方が9割』は難しい話術ではなく、誰でもすぐに実践できる心理学に基づいた言葉の作り方を学ぶことができます。
そして、最も大切なのは、犯人探しで終わらせるのではなく、「じゃあ、次はどうすればうまくいくかな?」と未来に向けた改善策を一緒に考える姿勢を示すことです。
一方的に解決策を押し付けるのではなく、本人に考えさせることで、当事者意識を引き出すことができます。
それでも改善が見られない場合は、一人で抱え込まず、上司に相談することも検討しましょう。
言い訳する人へ注意すること

言い訳をする人に対して注意や指導をする際には、伝え方を間違えると逆効果になるため、いくつかの点に気をつける必要があります。
絶対に避けるべきなのは、感情的に叱責したり、人格を否定したりすることです。
「いつもそうだ」「だから君はダメなんだ」といった言葉は、相手の心を閉ざさせ、反発心を煽るだけです。
また、他の社員がいる前で注意するなど、公の場で恥をかかせるのもNGです。
プライドを傷つけられた相手は、自己防衛のためにさらに頑なになり、行動の改善には繋がりません。
注意をする際は、一対一になれる静かな場所を選びましょう。
伝えるべき内容は、行動そのものに限定することが重要です。
「〇〇という言い訳をするのではなく、まず事実を報告してほしかった」というように、具体的な行動(Fact)と、それが周囲に与えた影響(Impact)を冷静に伝えることを心がけてください。
あくまで目的は相手を罰することではなく、成長を促すことであるというスタンスを忘れないことが大切です。

言い訳ばかりにならないためには?

自分自身が言い訳ばかりする人にならないためには、日頃からの意識と習慣が重要になります。
最も大切なのは、自分の行動に責任を持つという意識です。
物事がうまくいかなかった時に、すぐに他人や環境のせいにするのではなく、「自分に改善できる点はなかったか?」と自問自答する癖をつけましょう。
この自責の思考が、成長の原動力となります。
また、失敗を恐れすぎないことも大切です。
失敗は学びの機会であり、完璧な人間など存在しません。
小さな失敗を経験し、それを乗り越えることで自己肯定感が高まり、言い訳をする必要がなくなっていきます。
日々の業務においては、できないことは正直に伝える勇気も必要です。
安請け合いをして後で「時間がなかった」と言い訳をするよりも、最初に「その納期では難しいです」と相談する方が、よほど誠実であり、周囲からの信頼も得られます。
常に誠実であることを心がけ、言い訳のいらない働き方を目指しましょう。
『問題解決ドリル』で「事実→原因→次の一手」を書き出すワークを習慣化すると、他責の思考が減り、改善が早まります。
まとめ:言い訳ばかりする人の育ちを理解する

言い訳ばかりする人の行動とその背景について、多角的に解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 言い訳の根本には育った家庭環境が影響することが多い
- 親の過干渉や完璧主義が自己防衛的な性格を形成する
- 心理的には失敗への恐怖や低い自己肯定感が隠れている
- 特徴的な口癖として「でも」「だって」などが挙げられる
- 話を曖昧にしたり結論を先延ばしにする話し方をする
- 女性特有の協調性が裏目に出て言い訳に繋がる場合もある
- 極端な場合は病気の可能性も考えられるが自己判断は禁物
- 職場では責任転嫁により仕事ができないと評価されやすい
- 長期的には信頼を失い孤立するという悲惨な末路を辿る
- 対処法として責めずに事実確認を促すことが有効
- 注意する際は感情的にならず具体的な行動に焦点を当てる
- 自分で直すには失敗を認め他責にしない意識が不可欠
- 自分がならないためには日頃から誠実な行動を心がける
- 言い訳の背景にある育ちや心理を理解することが第一歩
- 相手を変えるのは難しく冷静な対話と適切な距離感が大切













