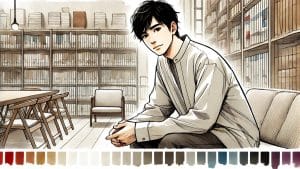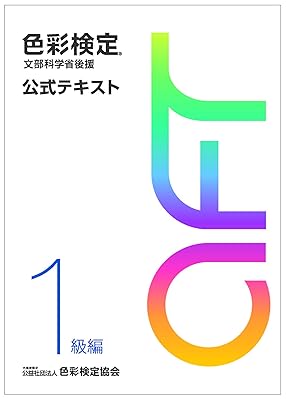色の資格に興味があるけれど、カラーコーディネートと色彩検定の違いがわからず、どちらのカラーコーディネーターの資格を選べばいいか迷っていませんか。
それぞれの難易度や合格率、試験日といった具体的な違いはもちろん、どっちが難しいのか、また併願は可能なのか、アドバンスクラスにいきなり挑戦できるのかといった点も気になるところでしょう。
中には、色彩検定は意味ないという声を聞いて不安に思ったり、そもそもこれらが国家資格なのか疑問に感じたりする方もいるはずです。
結局どっちがいいのか、この記事であなたの全ての疑問を解決し、最適な検定選びをサポートします。
- 2つの検定の目的と内容の根本的な違い
- 難易度や合格率、試験日の具体的な比較
- あなたに合った資格がどちらなのかという選び方
- それぞれの資格を活かせる仕事や分野
カラーコーディネートと色彩検定の違い|基本を解説

- そもそもカラーの検定とは?
- カラーコーディネーター検定と色彩検定の決定的な違い
- カラーコーディネーターの概要
- カラー検定は国家資格なのか
- 色彩検定は意味ないって本当?
そもそもカラーの検定とは?
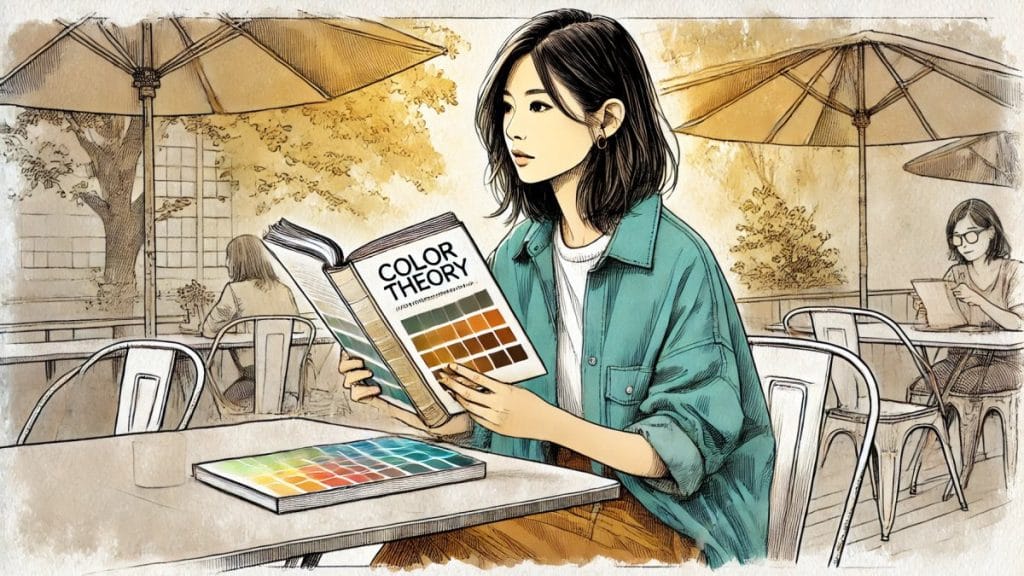
色に関する専門知識やスキルを証明するための民間資格が、カラーに関する検定です。
本来、色を扱う仕事に就くために必須の資格はありません。
しかし、資格を取得していることで、色彩理論や配色調和に関する体系的な知識を持っていることの客観的な証明になります。
これにより、就職や転職活動で有利に働くだけでなく、クライアントへの提案時にも説得力が増すでしょう。
具体的には、文部科学省が後援し知名度の高い「色彩検定®」や、東京商工会議所が主催しビジネスシーンに強い「カラーコーディネーター検定®」が代表的です。
その他にも、似合う色を提案するスキルを学ぶ「パーソナルカラリスト検定」や、アパレル業界に特化した「ファッション色彩能力検定」など、目的や専門分野に応じた多様な資格が存在します。
これらの資格で得た知識は、ファッションやインテリア、Webデザインなど、さまざまな分野で応用でき、仕事の幅を広げるきっかけにもなります。
趣味や日常生活をより豊かにするために学ぶ人も多く、幅広い目的で活用できるのがカラーの検定の特徴です。
カラーコーディネーター検定と色彩検定の決定的な違い

カラーコーディネーター検定と色彩検定は、どちらも色に関する知識を問う点で共通していますが、その目的と内容には明確な違いがあります。
どちらの資格が自分に合っているか判断するために、まずはこの根本的な違いを理解することが重要です。
大きな違いは、カラーコーディネーター検定がビジネスシーンでの実践的な活用に重きを置いているのに対し、色彩検定は基礎理論から応用まで、幅広く体系的な知識の習得を目指している点にあります。
以下の表で、両者の主な違いをまとめました。
| 項目 | 色彩検定 | カラーコーディネーター検定 |
|---|---|---|
| 主催団体 | 公益社団法人色彩検定協会 | 東京商工会議所 |
| 後援 | 文部科学省 | なし |
| 主な目的 | 色彩に関する幅広い知識と技能の向上 | ビジネスにおける色彩活用の実践力向上 |
| 内容の傾向 | ファッションやデザインなど、感性的な分野も含む | 工業製品や環境色彩など、ビジネス・理論寄りの分野が中心 |
| 知名度 | 非常に高い | 高い |
| おすすめの人 | 初心者、学生、幅広い分野で知識を活かしたい人 | ビジネスで実践的に使いたい人、専門性を高めたい社会人 |
このように、色彩検定は色の入門として、カラーコーディネーター検定はより専門的・実務的なスキルアップとして位置づけることができます。
カラーコーディネーターの概要
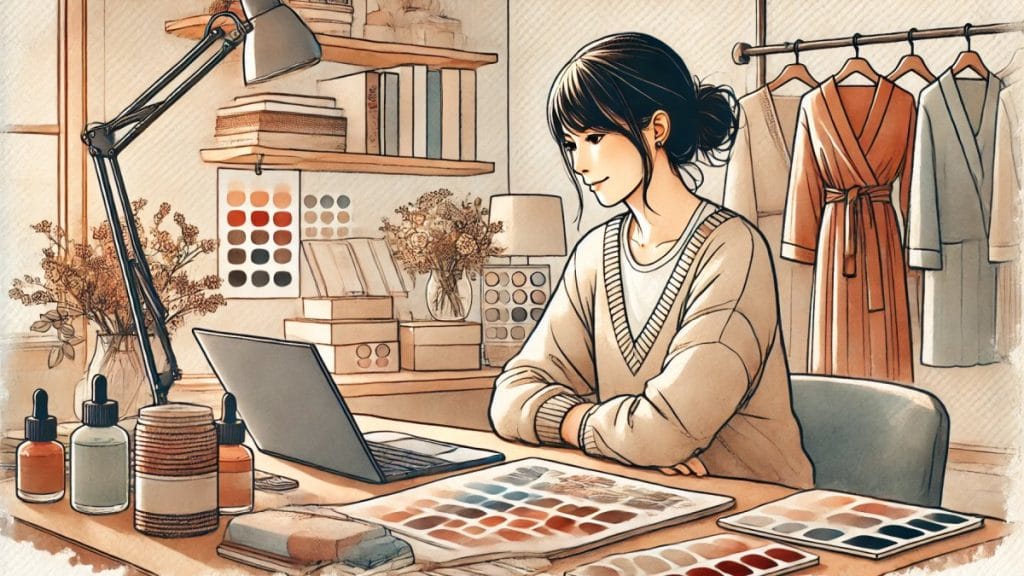
カラーコーディネーター検定試験は、東京商工会議所が主催する、色の知識をビジネスシーンで実践的に活用する能力を測る検定です。
特に、商品の企画・開発、店舗のディスプレイ、広告デザインといった商業分野や、建築・インテリアなどの環境色彩に関する専門知識が重視されます。
試験は2つのクラスに分かれています。
スタンダードクラス
色の基本的な性質や心理的効果、配色セオリーなど、色彩の基礎知識を学びます。
日常生活やビジネスの入門として役立つ内容です。
アドバンスクラス
スタンダードクラスの内容に加え、色彩調和論や色彩と文化、照明計画、ユニバーサルデザインなど、より専門的で実務に直結する知識が問われます。
企業の色彩計画や商品開発の第一線で活躍できるレベルを目指します。
理論的で学術的な側面が強く、ものづくりの現場で色の知識を論理的に活用したいと考えている社会人におすすめの資格といえるでしょう。
カラー検定は国家資格なのか

結論から言うと、カラーコーディネート検定と色彩検定のどちらも国家資格ではありません。
これらは、主催団体が独自に認定する民間の資格です。
ただし、色彩検定は文部科学省の後援を受けています。
これは、検定の内容や運営が一定の教育的水準を満たしていると認められていることを意味し、公的性質が強い資格といえます。
このため、学校教育の場で活用されたり、大学の単位認定の対象になったりすることもあり、社会的認知度や信頼性が非常に高いのが特徴です。
一方、カラーコーディネーター検定は東京商工会議所という経済団体が主催しており、ビジネス界での評価が高いという側面があります。
国家資格ではないものの、それぞれが持つ権威性や信頼性の背景を理解しておくことが大切です。
色彩検定は意味ないって本当?
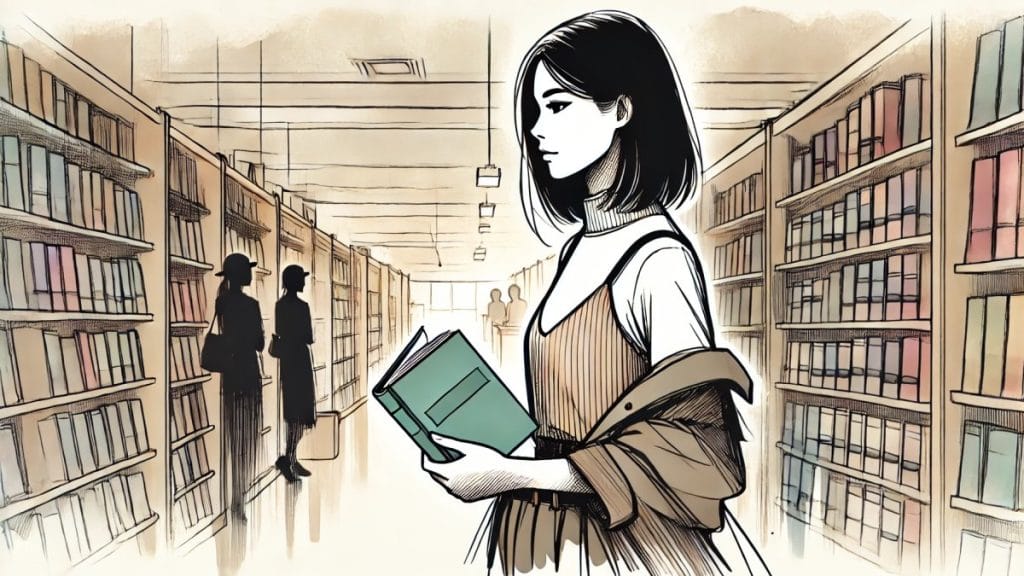
「色彩検定は意味ない」という意見を耳にすることがありますが、一概にそうとは言えません。
このように言われる背景には、資格を取得するだけで即座に専門職に就けるわけではない、という現実があります。
どの業界でも実務経験が重視されるため、資格はあくまでスタートラインに立つための一つのツールです。
しかし、色彩検定の学習を通じて得られるメリットは数多く存在します。
- 知識の体系化
感覚やセンスに頼りがちだった色の使い方を、理論に基づいて体系的に理解できます。 - 客観的なスキルの証明
色に関する知識レベルを客観的に示すことができ、就職活動や自己PRの際に強みとなります。 - 提案力の向上
顧客やチームに対して、なぜその配色なのかを論理的に説明できるようになり、提案の説得力が増します。 - 活躍分野の拡大
ファッション、インテリア、Web、広告など、さまざまな業界で応用可能な知識が身につきます。
資格取得をゴールとするのではなく、得た知識をいかに実務や生活で活かすかを考えることが重要です。
色彩検定は、色を扱う上での確かな土台となり、あなたの可能性を広げる決して無駄にはならない資格です。

カラーコーディネートと色彩検定の違い|試験で比較

- 検定ごとの難易度をチェック
- 最新の合格率で見る難しさ
- 結局どっちが難しいのか比較
- 年間の試験日とスケジュール
- アドバンスにいきなり挑戦できる?
- 併願受験はできるのか
検定ごとの難易度をチェック
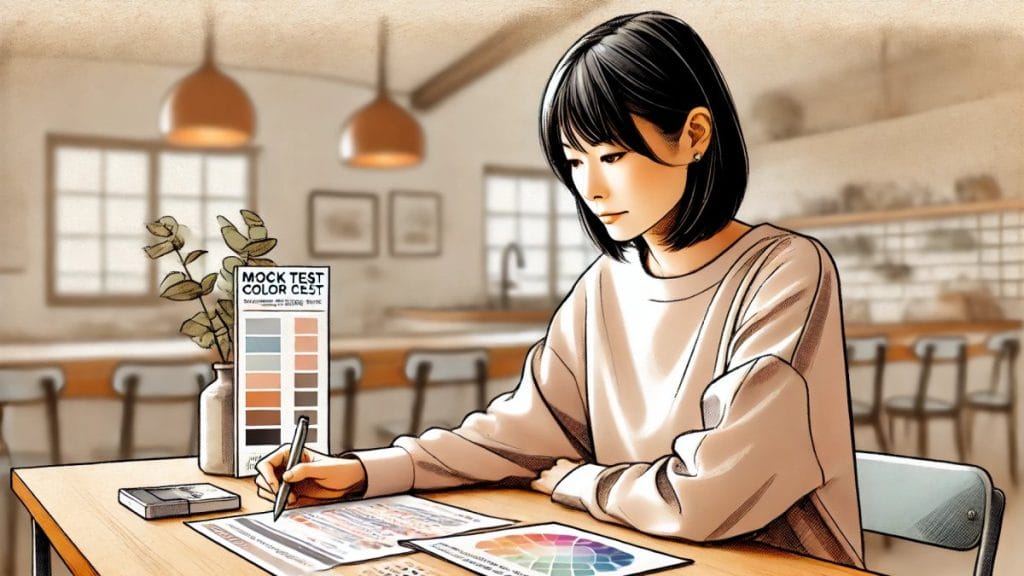
両検定の難易度は、級やクラスによって大きく異なります。
全体的な傾向として、色彩検定は3級やUC級など初心者向けのレベルが設定されており、段階的に学びやすい構成になっています。
一方、カラーコーディネーター検定は、スタンダードクラスでも色彩検定の2級に近いレベルの知識が求められることがあり、より専門的でビジネスに特化した内容となっています。
特に最上級レベルで比較すると、色彩検定1級は記述式の問題やカラーカードを使った実技試験が含まれ、非常に専門性が高く、合格率も低いため最難関とされています。
カラーコーディネーター検定のアドバンスクラスも高度な知識が求められますが、試験がマークシート方式であるため、試験形式の面では対策しやすいと感じる人もいるかもしれません。
最新の合格率で見る難しさ
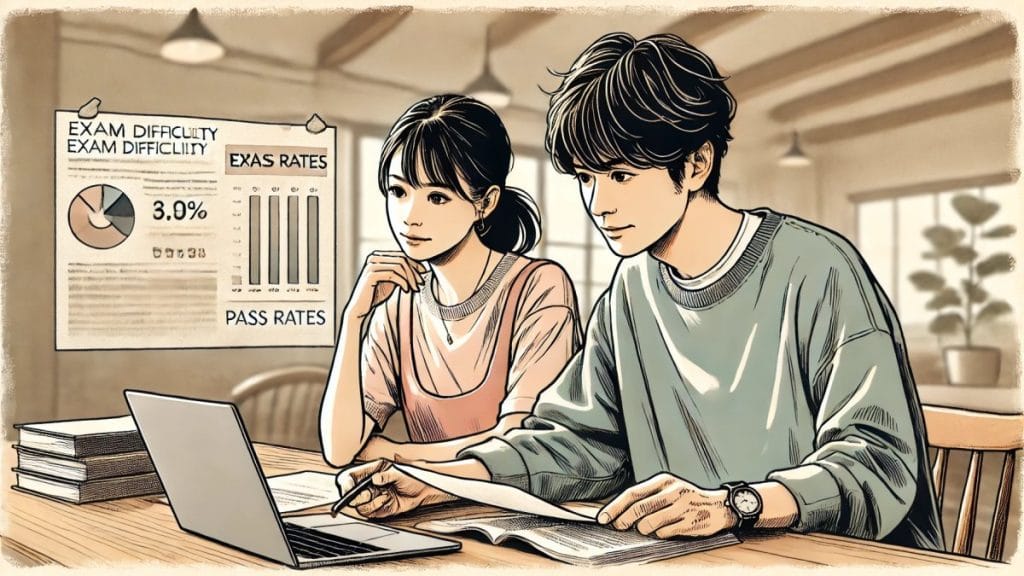
客観的な難易度を判断する指標として、合格率が参考になります。
以下は、公開されているデータに基づいた両検定の合格率です。
色彩検定(2023年度)
| 級 | 合格率 |
|---|---|
| 1級 | 41.4% |
| 2級 | 72.2% |
| 3級 | 74.1% |
| UC級 | 81.6% |
| ※色彩検定協会公式サイトの情報を参照 |
カラーコーディネーター検定(2023年度)
| クラス | 合格率 |
|---|---|
| アドバンスクラス | 48.8% |
| スタンダードクラス | 74.3% |
| ※東京商工会議所公式サイトの情報を参照 |
3級やスタンダードクラスといった入門レベルでは、どちらも70%以上の高い合格率です。
しかし、2級以上になると差が見られ、特に最上級の色彩検定1級は40%台と、アドバンスクラスよりも合格率が低くなっています。
この数値からも、色彩検定1級が特に難関であることがうかがえます。
結局どっちが難しいのか比較

結論として、最上級レベルにおいては、一般的に「色彩検定1級」の方が難しいとされています。
その理由は、試験形式にあります。
カラーコーディネーター検定アドバンスクラスがマークシート方式であるのに対し、色彩検定1級はマークシートの1次試験に合格した後、さらに記述式と実技(カラーカードの貼り付け)からなる2次試験を突破しなければなりません。
単に知識を暗記するだけでなく、それを応用して実際に手を動かすスキルまで求められるため、総合的な対策が必要になります。
ただし、これはあくまで試験形式上の比較です。
カラーコーディネーター検定は、より学術的で専門的な用語が多く出題されるため、学習内容そのものに難しさを感じる人もいます。
最終的には、ご自身の得意な学習スタイルや目指す分野によって、難易度の感じ方は変わってくるでしょう。
年間の試験日とスケジュール

受験を計画する上で、試験日の確認は不可欠です。
両者の試験形式とスケジュールには大きな違いがあります。
| 検定名 | 試験日 | 試験方式 |
|---|---|---|
| 色彩検定 | 夏期検定:例年6月 冬期検定:例年11月・12月 | 会場でのペーパー試験 (マークシート、一部記述・実技) |
| カラーコーディネーター検定 | 時期による (例: 夏期 6月~7月, 冬期 10月~11月) | IBT方式(自宅PC) CBT方式(テストセンター) |
色彩検定は、年に2回、全国の指定会場で一斉に行われる従来型の試験です。
一方、カラーコーディネーター検定は、試験期間内であれば自分の都合の良い日時と場所(自宅またはテストセンター)を選んで受験できるIBT/CBT方式を採用しています。
このため、スケジュール調整のしやすさではカラーコーディネーター検定に大きなメリットがあります。
アドバンスにいきなり挑戦できる?
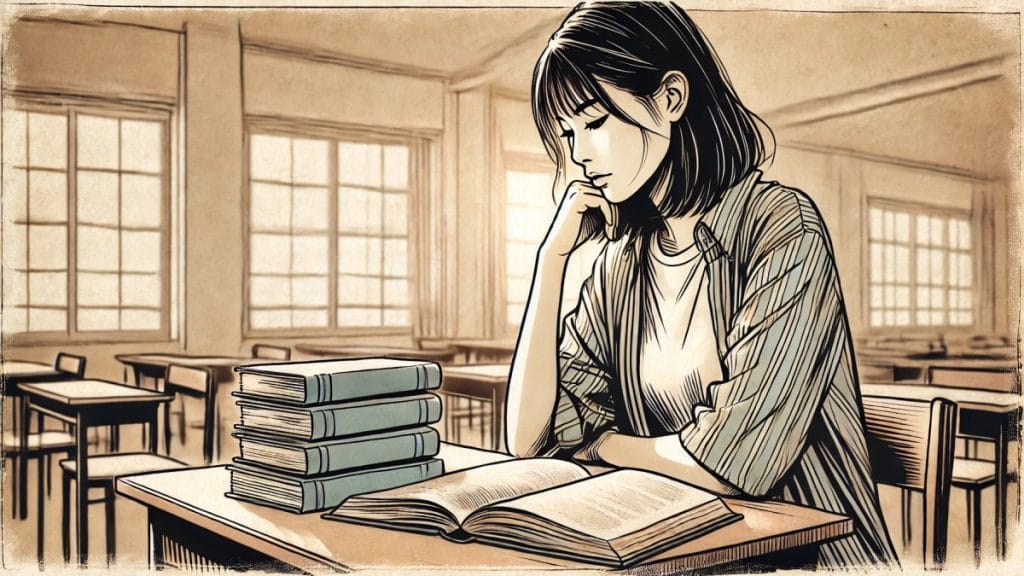
どちらの検定も最上位のアドバンスクラスや1級からいきなり挑戦することが可能です。
両検定ともに受験資格に学歴や年齢、実務経験などの制限を設けていません。
したがって、下の級から順番に受験する必要はなく、自分の知識レベルに合わせて目標の級を直接目指すことができます。
ただ、注意点として、アドバンスクラスや1級の試験範囲には、下位級の内容が基礎知識として含まれています。
そのため、色彩の学習が全くの初めてという方が、基礎を飛ばして最上級に挑戦するのは、学習効率の面であまりおすすめできません。
公式テキストは下の級から揃え、体系的に学習を進めることが合格への近道となるでしょう。
併願受験はできるのか
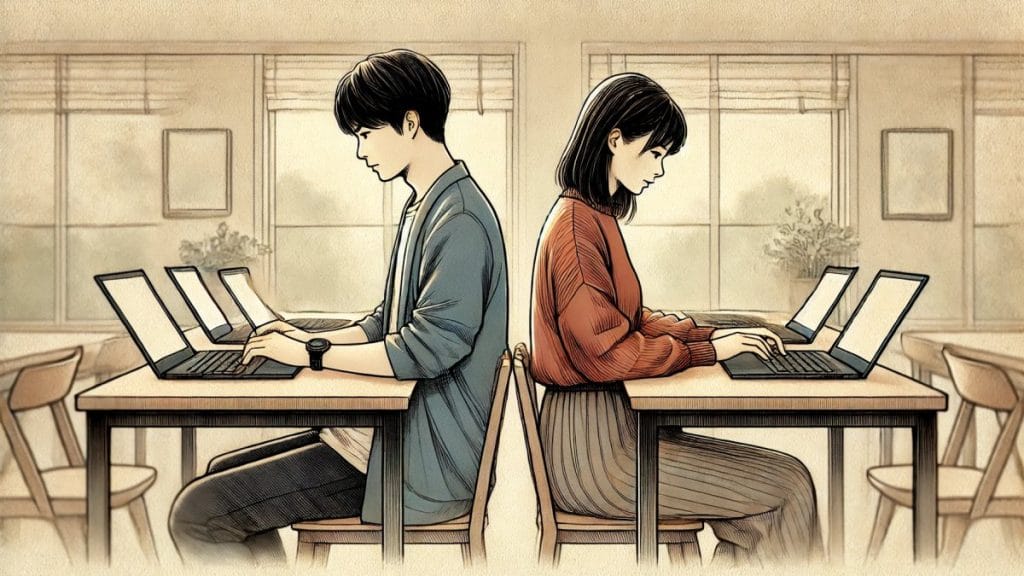
併願して両方の資格を取得することも可能です。
主催団体が異なり、試験日や試験期間も重複しない場合が多いため、スケジュールをうまく管理すれば同一年内に両方の資格を目指せます。
特にカラーコーディネーター検定は受験日時の自由度が高いため、色彩検定の試験日を避けながら計画を立てやすいでしょう。
両方の資格を学ぶことには、知識を多角的に深められるというメリットがあります。
例えば、色彩検定で幅広い基礎知識を身につけ、カラーコーディネーター検定でビジネス寄りの専門性を補うといった形で、相互に知識を補完し合うことができます。
ただし、学習範囲が広がり負担も大きくなるため、計画的に学習を進めることが重要です。
結局どっちがいい?カラーコーディネートと色彩検定の違い

- 色彩検定は文部科学省後援で知名度が高い
- カラーコーディネーター検定は東京商工会議所主催でビジネス寄り
- どちらも国家資格ではなく民間資格
- 初心者や学生には段階的に学べる色彩検定がおすすめ
- ビジネスで実践的に活用したいならカラーコーディネーター検定
- 最上級の難易度は実技のある色彩検定1級の方が高い傾向
- 入門レベルの合格率はどちらも70%以上と高い
- 色彩検定1級の合格率は40%前後で難関
- カラーコーディネーター検定アドバンスの合格率は50%弱
- 色彩検定は年2回会場で実施
- カラーコーディネーター検定はPCで期間内に受験可能
- どちらもいきなり上の級を受験できる
- 主催団体が違うため併願も可能
- 色彩検定は意味ないわけではなく知識の土台となる
- 自分の目的やキャリアプランに合わせて選ぶことが最も重要