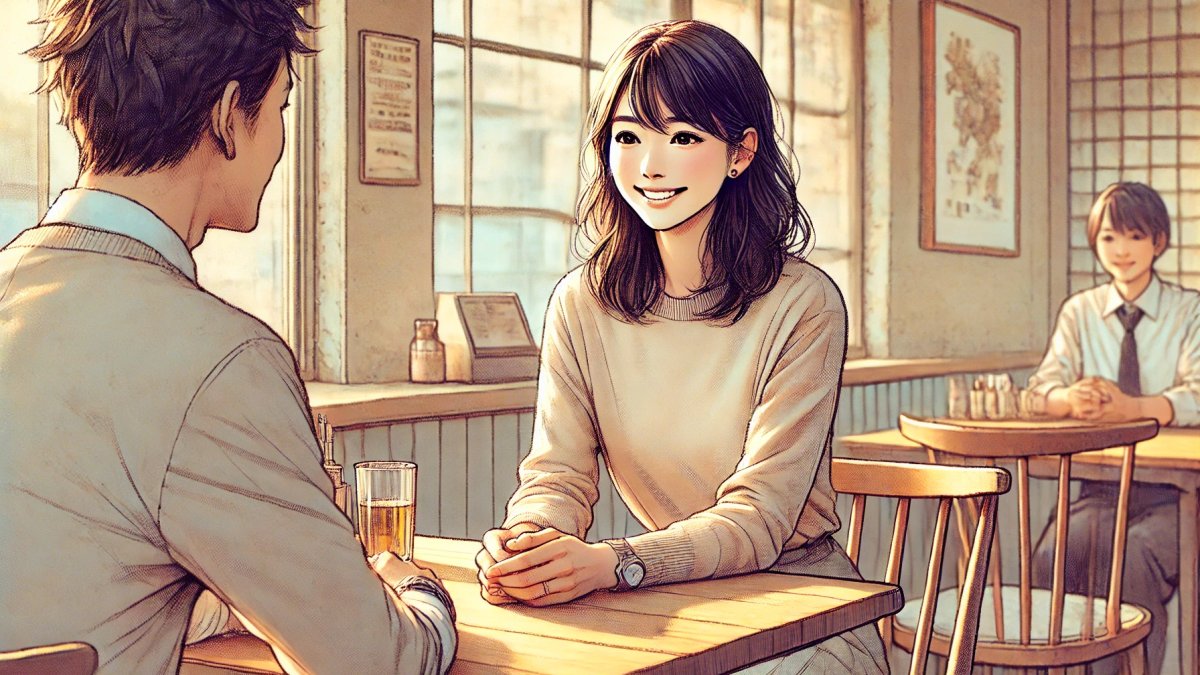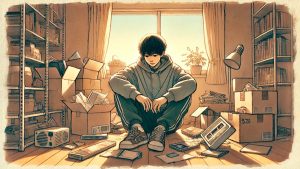「やる気にさせるのが上手い人」になるには、どのようなスキルが必要なのでしょうか。
多くの管理職や先輩が、人を育てるのが上手い人や、部下や後輩のモチベーションを上げてくれる人になりたいと願っています。
人を動かすのが上手い人の特徴は?あるいは、そもそもモチベーションの高い人はどんな特徴があるのでしょうか。
その答えは、心理学に基づいたアプローチや具体的な方法に隠されています。
単に人をやる気にさせる人は、人をのせるのがうまい人というだけでなく、教えるのがうまい人の特徴も兼ね備えているものです。
一方で、良かれと思った言動が相手の意欲を奪う「やる気を削ぐ天才」になってしまう危険性も存在します。
この記事では、向上心のある人の特徴を伸ばし、相手の心に響く魔法の言葉を見つけるためのヒントを解説します。
- やる気を引き出す人と削いでしまう人の決定的な違い
- モチベーションの源泉となる心理学の基礎知識
- 部下や後輩の意欲を高める具体的なコミュニケーション術
- 自身のモチベーションを管理し、成長を促すための方法
やる気にさせるのが上手い人の共通点と特徴
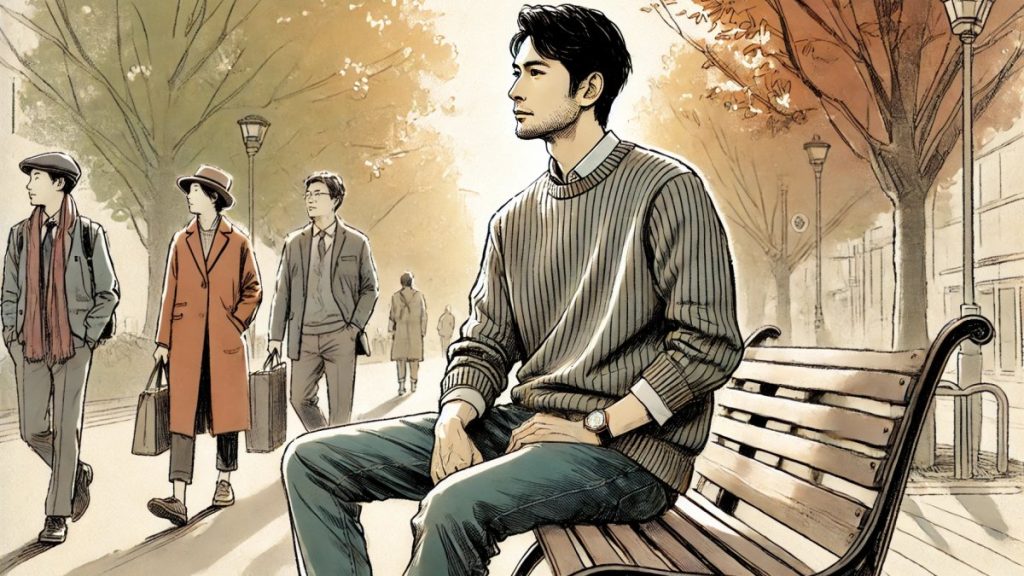
- 人を動かすのが上手い人の特徴は?
- モチベーションの高い人はどんな特徴がある?
- 向上心のある人の特徴は?
- 人を育てるのが上手い人のコミュニケーション術
- 逆効果になる「やる気を削ぐ天才」の行動
人を動かすのが上手い人の特徴は?
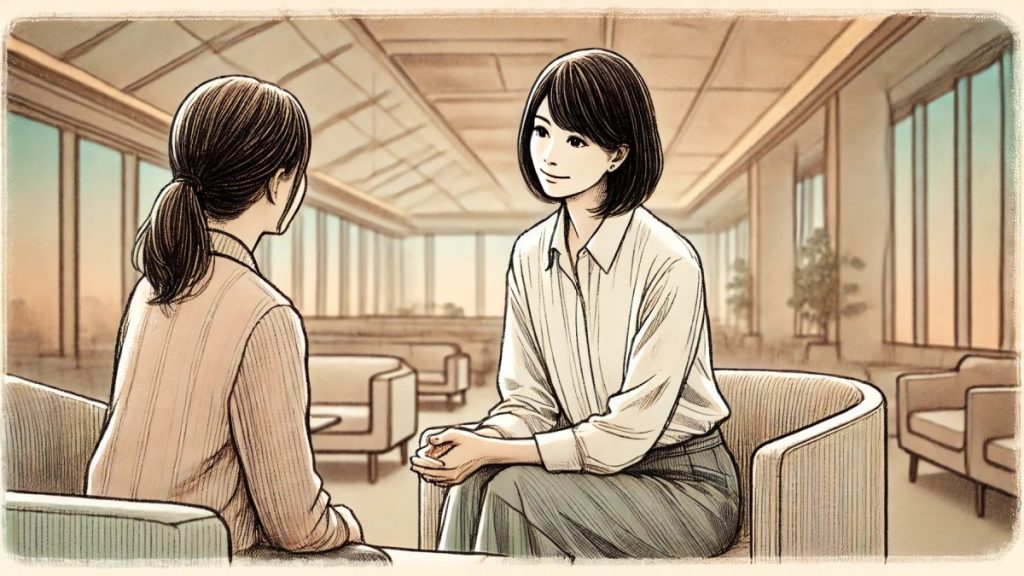
人を動かすのが上手い人は、単に指示が的確なだけではありません。
彼らは、相手に対する深い理解と、人間的な魅力を兼ね備えていることが最大の特徴です。
アンケート調査によれば、メンバーのモチベーションを上げるのが上手い上司は、人間的にも魅力的だと感じる人が85%にものぼります。
この魅力は、主に以下の3つの要素から構成されていると考えられます。
- 一貫性のある言動
言うこととやることが一致しており、信頼できます。例えば、「責任は私が取る」と公言し、部下が失敗した際に実際にその言葉通りに行動する上司は、部下から絶大な信頼を得るでしょう。この信頼が、「この人のために頑張ろう」という気持ちを引き出します。 - ポジティブな姿勢
困難な状況でも前向きな姿勢を崩さず、解決策を探す姿は、周囲に安心感と希望を与えます。逆に、頻繁にため息をついたり、他人のせいにしたりする態度は、チーム全体の士気を著しく低下させます。ナポレオンの「リーダーとは希望を配る人のことだ」という言葉の通り、ポジティブなオーラそのものが周囲を動かす力となるのです。 - 優れた共感力と傾聴力
相手の意見や感情を頭ごなしに否定せず、まずは受け止めて真摯に耳を傾けるスキルを持っています。アマゾンのジェフ・ベゾスが従業員からのフィードバックを意思決定に活かしていたように、相手の立場を尊重する姿勢が、自発的な行動を促す土台となります。
これらの特徴は、スキルやテクニック以前の、人としてのあり方そのものに関わる部分です。
人を動かす力を手に入れるには、まず自分自身が人として信頼され、尊敬される存在であることが不可欠だと言えます。
モチベーションの高い人はどんな特徴がある?
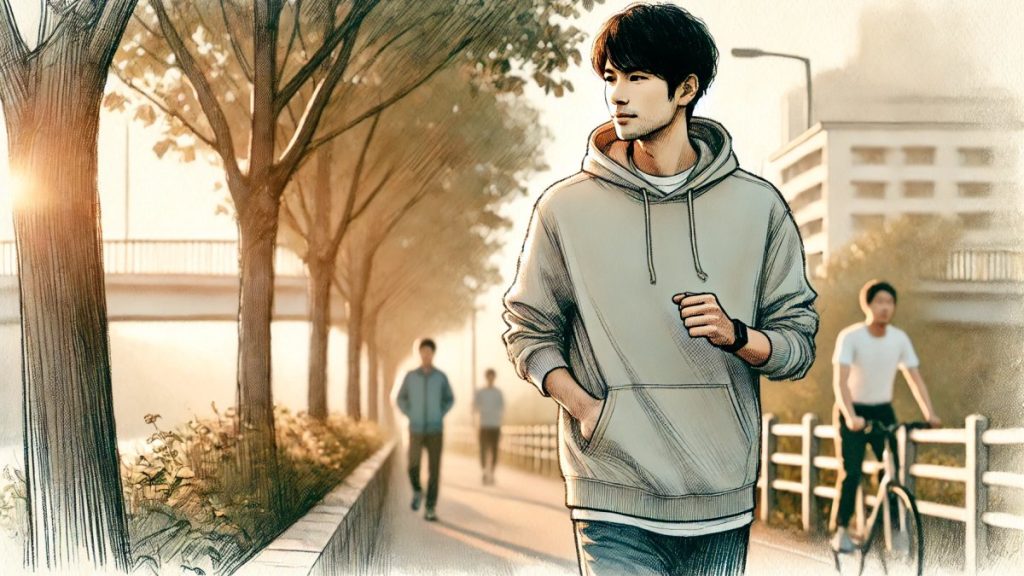
モチベーションの高い人は、自らの内部からエネルギーを生み出す力を持っています。
彼らは外部からの報酬や評価だけに頼らず、仕事そのものに喜びや意義を見出す内発的動機づけが非常に強いという特徴があります。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
1. 明確な目標と自己成長への意欲
モチベーションの高い人は、自分がどこへ向かっているのかを明確に理解しています。
それは会社から与えられた目標だけでなく、「自分はこうなりたい」という個人的なビジョンを含みます。
そして、その目標達成に向けた努力や挑戦のプロセス自体を楽しめるのです。
彼らにとって仕事は、自己を成長させるための絶好の機会と捉えられています。
2. 失敗を恐れないチャレンジ精神
彼らは失敗を「終わり」ではなく、学びの機会と捉えることができます。
これは、心理学で言う「成長マインドセット」を持っていることの表れです。
自分の能力は固定的ではなく、努力次第で伸ばせると信じているため、困難な課題にも積極的に挑戦し、そこから得られる経験を次の成功へと繋げていきます。
3. 主体性と自己管理能力
誰かに言われたからやるのではなく、「自分がやるべきだ」という主体性を持って仕事に取り組みます。
また、目標達成のために自分の時間や行動を効率的に管理する能力にも長けています。
例えば、集中力が途切れそうなときでも、「あと5分だけやってみよう」と自らを鼓舞し、作業を再開させることで脳の「作業興奮」を促すといった工夫を自然に行っています。
このように、モチベーションの高い人は、自らの心を巧みにコントロールし、常に前向きなエネルギーを維持する術を身につけているのです。
向上心のある人の特徴は?

向上心のある人は、現状に満足することなく、常に自己の成長と改善を求める姿勢を持っています。
この探求心は、個人のパフォーマンスを高めるだけでなく、周囲にも良い影響を与え、組織全体の活力を生み出す源泉となります。
向上心のある人に見られる主な特徴は以下の通りです。
- 知的好奇心が旺盛
自分の専門分野はもちろん、それ以外の新しい知識やスキルに対しても常にアンテナを張っています。彼らは学ぶこと自体に喜びを感じ、「なぜだろう?」「もっと良い方法はないか?」と自ら問いを立てて探求することを厭いません。 - 素直さとフィードバックへの感謝
他人からのアドバイスや批判を、自分を成長させるための貴重な情報として素直に受け入れます。自分の間違いを認め、改善しようとする柔軟な思考を持っているため、成長のスピードが非常に速いのが特徴です。 - 行動力と挑戦
ただ学ぶだけでなく、得た知識を実践に移す行動力があります。彼らは、理解度ぎりぎりの少し難しい課題にあえて挑戦することが、脳とスキルを最も成長させることを感覚的に理解しています。失敗のリスクを恐れず、まずはやってみるという姿勢が、彼らをさらなる高みへと導きます。
ただし、注意点として、向上心が高すぎるあまり、自分にも他人にも完璧を求めすぎてしまうことがあります。
時には自分を追い込みすぎたり、周囲のペースを考えずに行動して反感を買ったりする可能性も否定できません。
向上心という素晴らしいエネルギーを、自分と周囲の双方にとってプラスの力として活用するには、時として休息を取ることや、他者と協調する視点も重要になります。
人を育てるのが上手い人のコミュニケーション術
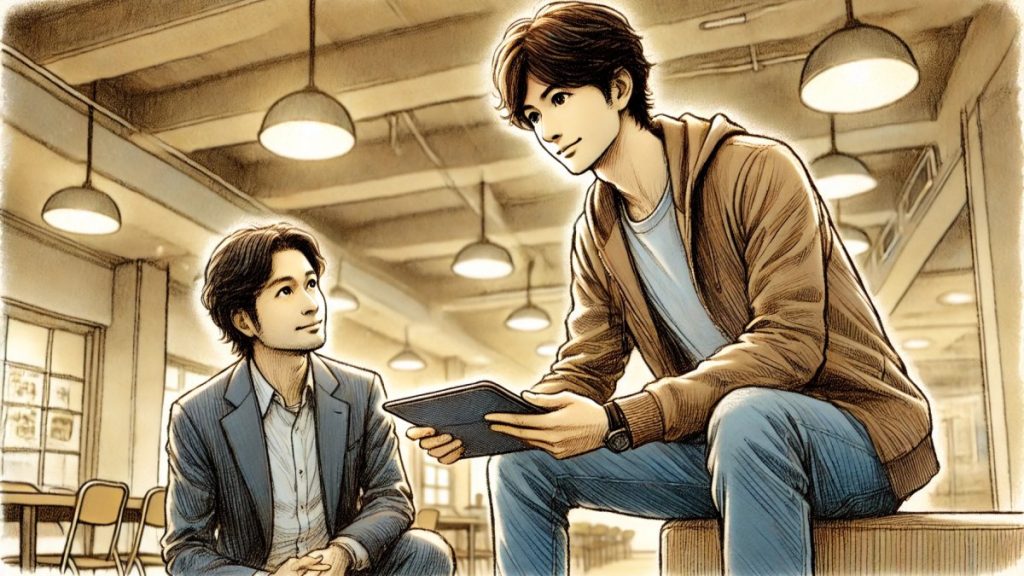
人を育てるのが上手い人は、相手の内なる可能性を引き出すための、巧みなコミュニケーション術を身につけています。
それは一方的に教え込むのではなく、相手の自律性を尊重し、自ら気づき、成長していくプロセスを支援する関わり方です。
その中心となるのが、以下の2つの柱です。
- アクティブリスニング(傾聴)
相手の話をただ聞くのではなく、深く理解し、共感しようとする姿勢です。相槌や質問を通じて相手が話しやすい雰囲気を作り、内面にある考えや感情を引き出します。これにより、相手は「自分のことを理解してくれている」という安心感と信頼感を抱き、心を開いて相談できるようになります。 - 効果的なフィードバック
フィードバックの目的は、相手を評価することではなく、成長を促すことです。人を育てるのが上手い人は、この点を深く理解しています。
| 良いフィードバックの例 | 悪いフィードバックの例 |
|---|---|
| 「今回の資料、Aの部分の分析が特に鋭いね。Bをもう少し深掘りすると更に良くなると思うよ。」 | 「この資料、全然ダメだね。やり直して。」 |
| 行動や事実(プロセス)に焦点を当て、具体的かつ建設的 | 人格や能力を否定し、抽象的で一方的 |
| 肯定的な点から伝え、改善点を提案する形式 | 否定的な点から入り、相手を萎縮させる |
特に重要なのが、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授が提唱する「マインドセット理論」に基づいた褒め方です。
才能や能力といった固定的なものを褒めるのではなく、努力や工夫、挑戦した姿勢といったプロセスを具体的に褒めることで、相手の「成長マインドセット」を育みます。
フィードバックは相手の成長を客観的な事実に基づいて支援する行為であり、近年その重要性が改めて注目されていると報告されています。
これにより、相手は失敗を恐れずに新しいことに挑戦する意欲を持つようになります。
このように、人を育てるコミュニケーションとは、相手を統制するのではなく、信頼関係を基盤として、相手の自律的な成長を支援する技術であると言えるでしょう。
逆効果になる「やる気を削ぐ天才」の行動

良かれと思って取った行動が、かえって相手のモチベーションを著しく低下させてしまうことがあります。
こうした「やる気を削ぐ天才」にならないためには、失敗パターンを知っておくことが非常に重要です。
アンケート調査から明らかになった、部下や後輩のやる気を削ぐ代表的な行動パターンには、以下のようなものがあります。
- 頭ごなしに叱る、人格を否定する
「なぜできないんだ」と感情的に叱責したり、「君には向いていない」と人格を否定したりする言動です。これは相手に恐怖心と無力感を植え付け、挑戦する意欲を完全に奪ってしまいます。このような人格否定や精神的な攻撃はパワーハラスメントに該当する可能性があり、事業主には防止措置を講じることが義務付けられていると明らかになっています。
>> 厚生労働省(2023) - 過剰なフォロー、過保護
相手の成長を信じず、失敗を恐れるあまり、細かく指示を出したり、先回りして仕事を取り上げてしまったりする行動です。「どうせ自分がやった方が早い」という態度は、相手から学びの機会と責任感を奪い、指示待ち人間にしてしまいます。 - 手柄の横取り、ミスの押し付け
部下の成功を自分の手柄のように話し、自分のミスは部下や環境のせいにする上司です。このような不誠実な態度は信頼関係を根底から破壊し、部下は「この人のために頑張っても無駄だ」と感じるようになります。 - 無関心、放置
部下が努力している過程や成果に全く関心を示さない、あるいは見て見ぬふりをする態度です。人は誰しも、自分の頑張りを認められたいという承認欲求を持っています。無視されることは、叱責されること以上にモチベーションを低下させる要因となり得ます。
これらの行動に共通するのは、相手を「自分の思い通りに動かすための道具」として見ている点です。
相手を尊重し、一人の人間として信頼する姿勢が欠けていることが、結果的にやる気を削ぐ最悪の行動に繋がってしまうのです。

やる気にさせるのが上手い人が使う心理学と方法

- 人をやる気にさせる人が使う心理学とは
- のせるのがうまい人が使う魔法の言葉
- 教えるのがうまい人の特徴は?
- モチベーションを上げてくれる人の具体的な方法
- あなたもやる気にさせるのが上手い人になれる
人をやる気にさせる人が使う心理学とは

人をやる気にさせるのが上手い人は、経験則や勘だけに頼るのでなく、心理学的な理論を背景としたアプローチを自然と実践しています。
特に重要となるのが、「人はどのような時に自ら進んで行動したくなるのか」を解き明かす理論です。
その代表格が、心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論」です。
この理論では、人間には生まれつき以下の3つの心理的欲求が備わっており、これらが満たされることで内発的動機づけ(自らの内側から湧き出るやる気)が高まるとされています。
- 自律性(Autonomy)
自分の行動を自分自身で選択し、決めたいという欲求です。他者から強制されたり、統制されたりするのではなく、「自分で決めた」という感覚がモチベーションの源泉となります。例えば、仕事の進め方にある程度の裁量権を与えることは、この自律性を満たす上で非常に効果的です。 - 有能感(Competence)
自分は能力があり、課題を達成できると感じたいという欲求です。挑戦的な課題を乗り越えた時の達成感や、他者からの適切なフィードバックによってこの有能感は高まります。「やればできる」という感覚は、次の挑戦への意欲を引き出します。 - 関係性(Relatedness)
他者と尊重し合える、安全で良好な関係を築きたいという欲求です。チームメンバーや上司と信頼関係で結ばれ、組織の一員として受け入れられていると感じることが、安心して仕事に取り組むための心理的な土台となります。
人をやる気にさせるのが上手い人は、これらの欲求を意識的、あるいは無意識的に満たす環境作りをしています。
近年の教育分野の研究においても、学習者の自律性・有能感・関係性の欲求を満たすことが、学習意欲の向上に繋がると報告されています。
報酬や罰則といった外発的な動機づけ(アメとムチ)に頼りすぎず、相手の内なる力を引き出すことこそが、持続的なモチベーションを生み出す鍵であることを理解しているのです。
のせるのがうまい人が使う魔法の言葉

人をのせるのがうまい人は、相手の心に火を灯す「魔法の言葉」を持っています。
それは、単なるお世辞や褒め言葉ではありません。
相手の自己肯定感を高め、行動を促すための、心理学に基づいた効果的な声かけです。
特に効果的な魔法の言葉は、相手の「行動」や「プロセス」に焦点を当てたものです。
1. 努力や工夫を具体的に認める言葉
- NG例:「すごいね!天才だね!」
- OK例:「毎日コツコツ準備していたのを見ていたよ。その努力がこの結果に繋がったんだね。」
才能や結果だけを褒めると、相手は「成功しない自分には価値がない」と感じ、失敗を恐れる「固定マインドセット」に陥りがちです。
一方、努力の過程を具体的に認めることで、「頑張れば成長できる」という「成長マインドセット」が育まれ、挑戦への意欲が高まります。
『みんなのフィードバック大全』は、相手の成長を促すための具体的な言葉選びやタイミングを学ぶのに役立ちます。
2. 存在そのものや貢献を承認する言葉
- NG例:(特に無し。無関心が一番の問題)
- OK例:「君がチームにいてくれて本当に助かるよ。」「陰で支えてくれていることに感謝しているよ。」
人は誰しも、自分の存在が認められ、誰かの役に立っていると感じたいものです。
特に、目立たないけれど重要な仕事をしている人に対して、その貢献を承認する言葉は絶大な効果を発揮します。
誰も見ていないと思っていた努力を認められた時、人は「もっと頑張ろう」と強く思うものです。
3. 信頼と期待を伝える言葉
- NG例:「ちゃんとできるの?」
- OK例:「君ならできると信じているよ。何かあったら責任は私が取るから、思い切ってやってごらん。」
相手の能力を信じ、裁量権を与える言葉は、相手の自律性と有能感を刺激します。
失敗を恐れずに行動できる心理的な安全性を確保することで、相手は本来持っている能力を最大限に発揮できるようになります。
これらの言葉は、上辺だけのテクニックで使うとすぐに見抜かれてしまいます。
相手を心から信頼し、その成長を願う気持ちが伴ってこそ、真の「魔法の言葉」となるのです。

教えるのがうまい人の特徴は?
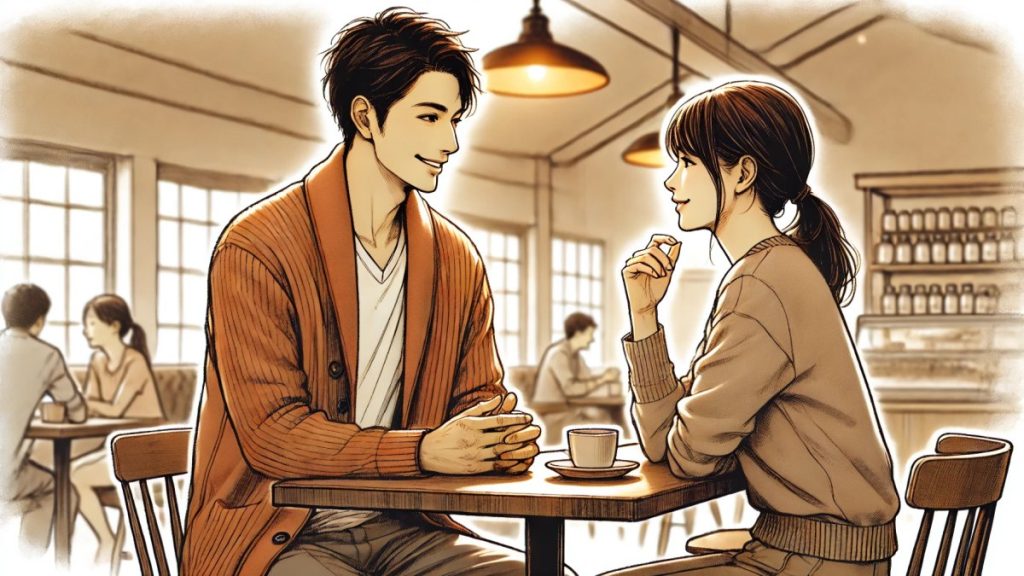
教えるのがうまい人は、豊富な知識を持っているだけではありません。
その知識を相手が理解し、実践できるようになるまでのプロセスをデザインする能力に長けています。
彼らの特徴は、一方向的な「ティーチング」ではなく、双方向的な「コーチング」や「ファシリテーション」の視点を持っている点にあります。
主な特徴として、以下の点が挙げられます。
- 相手の現在地を把握する
教えるのがうまい人は、まず相手が「何を知っていて、何を知らないのか」「何が得意で、何が苦手なのか」を正確に把握することから始めます。相手のレベルや理解度に合わせずに一方的に情報を浴びせても、相手は消化不良を起こすだけです。対話を通じて相手の現在地を確認し、最適なスタート地点を設定します。 - 全体像とゴールを先に示す
いきなり細部の作業を教えるのではなく、「今からやることは、全体のこの部分にあたる」「この作業の目的は〇〇だ」というように、まず全体像(森)を示してから、個々の作業(木)の説明に入ります。これにより、教わる側は自分の作業の意味や位置づけを理解でき、モチベーションを維持しやすくなります。 - 「やらせてみる」ことを重視する
説明を聞くだけでは、スキルは身につきません。教えるのがうまい人は、安全な範囲で積極的に「やらせてみる」機会を作ります。そして、失敗してもそれを責めるのではなく、なぜそうなったのかを一緒に考え、改善策を導き出すサポートをします。この試行錯誤のプロセスこそが、最も効果的な学習方法であることを知っています。 - 質問しやすい雰囲気を作る
「こんなことを聞いたら馬鹿だと思われるかもしれない」という不安は、学習の大きな妨げになります。教えるのがうまい人は、日頃からオープンなコミュニケーションを心がけ、「どんな質問でも歓迎する」という姿勢を示しています。これにより、相手は安心して疑問を解消し、理解を深めることができます。
要するに、教えるのがうまい人とは、情報の伝達者である以上に、相手の「学びの伴走者」としての役割を果たすことができる人なのです。
モチベーションを上げてくれる人の具体的な方法
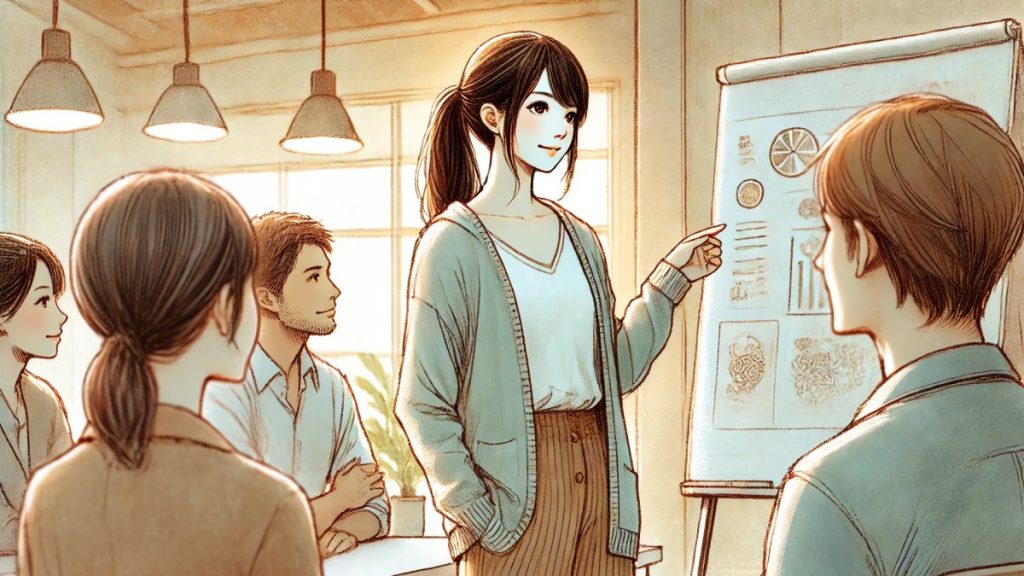
モチベーションを上げてくれる人は、日常の関わりの中で、相手のやる気スイッチを押すための具体的な方法を実践しています。
それは大掛かりな制度やイベントではなく、日々の些細な言動の積み重ねであることがほとんどです。
以下に、誰でも明日から実践できる具体的な方法をいくつか紹介します。
1. 小さな成功体験をデザインし、褒める
いきなり大きな目標を与えるのではなく、少し頑張れば達成できるような小さなタスクを設定します。
そして、それを達成できた際には、すかさず「仕事が速いね!」「丁寧な作業だね!」といった形で具体的に褒めることが重要です。
小さな成功体験と承認の積み重ねが、「自分はできる」という有能感を育み、より大きな課題に挑戦する土台となります。
2. タイミングを見計らった声かけ
相手が頑張っている、まさにその瞬間に声をかけることは非常に効果的です。
例えば、締め切り間近で残業している時に「もうひと踏ん張り、頑張ろう!」と声をかけたり、難しい課題に悩んでいる時に「少し休憩したら?」と気遣ったりする一言が、相手の心を支え、もう一度頑張る力を与えます。
3. 相談しやすい環境を作る
日頃から部下や後輩に関心を持ち、彼らの話に耳を傾ける姿勢を見せることが大切です。
仕事の進捗だけでなく、彼らが興味を持っていることや価値観について知ろうとすることで、信頼関係が構築されます。
これにより、彼らは問題や困難に直面した際に、一人で抱え込まずに安心して相談できるようになります。
『人は聞き方が9割』を読めば、相手が安心して話せる雰囲気作りのコツがわかり、相談される機会が増えるかもしれません。
4. 自分自身が楽しんで仕事に取り組む
前述の通り、上司や先輩が誰よりも仕事に情熱を注ぎ、楽しんでいる姿を見せること自体が、最も強力なモチベーション向上策となり得ます。
その姿は「自分もあんな風になりたい」という憧れや目標となり、部下や後輩の自発的なやる気を引き出すのです。
これらの方法は、特別なスキルを必要とするものではありません。
相手への関心と尊重、そして「共に成長したい」という気持ちがあれば、誰でも実践可能なのです。
あなたもやる気にさせるのが上手い人になれる

ここまで見てきたように、「やる気にさせるのが上手い人」とは、天性の才能を持つ特別な人だけを指すのではありません。
心理学に基づいた人間理解と、日々の具体的な行動の積み重ねによって、誰でもそのスキルを身につけることが可能です。
この記事で紹介した内容を参考に、あなたも周囲の力を最大限に引き出すリーダーを目指しましょう。
- 人を動かす基本は信頼関係の構築から
- 相手の努力やプロセスを具体的に褒める
- 結果だけでなく挑戦した姿勢を評価する
- 内発的動機づけを尊重し、自律性を支援する
- 「自分で決めた」という感覚を持たせることが重要
- 小さな成功体験を積み重ねさせ、有能感を育む
- 相手の話を真摯に聴くアクティブリスニングを実践する
- 頭ごなしの叱責や人格否定は絶対に行わない
- 過剰なフォローは相手の成長機会を奪うと心得る
- 自分自身が仕事を楽しむ姿を見せる
- 失敗は学びの機会と捉える「成長マインドセット」を促す
- 相手の現在地を理解してから指導を始める
- 仕事の全体像や目的を共有し、意味を伝える
- 心理的な安全性を確保し、質問しやすい雰囲気を作る
- 感謝の気持ちを言葉にして伝えることを忘れない